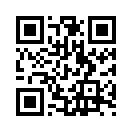2019年05月21日
なんてこったい!
GOGO左官店にようこそ!
久々に んだブログの設定を変えたついでに一番訪問の多い記事を見てみたら、なんと写真が違う写真になっている部分が
なんということでしょう!
ブログ書き初めで慣れないとき、写真データ番号が同じで上書きしたのか?
ひえーーーー
直し方がわからない!
写真データーもたくさんあるから探せない
むむむ"(-""-)"
きっと他のブログ記事も同じ現象があるに違いない・・・
どうしよう。見て下る皆さんに申し訳ない
ごめんなさいいいい
次からは気を付けて写真投稿しよう・・・
久々に んだブログの設定を変えたついでに一番訪問の多い記事を見てみたら、なんと写真が違う写真になっている部分が

なんということでしょう!
ブログ書き初めで慣れないとき、写真データ番号が同じで上書きしたのか?
ひえーーーー

直し方がわからない!
写真データーもたくさんあるから探せない

むむむ"(-""-)"
きっと他のブログ記事も同じ現象があるに違いない・・・
どうしよう。見て下る皆さんに申し訳ない

ごめんなさいいいい

次からは気を付けて写真投稿しよう・・・
2016年02月22日
いなばしり作成中
GOGO左官店にようこそ!
本日は2月というのに暖かい陽気にめぐまれました
ちょっと手が空いたので、我が家のいなばしりを作成中。
前は「いなばしり=稲はしり」だと思っていたら、どうやら「犬走り」が本当の漢字ということが私の中で発覚
WIKIでは「犬走り→いぬはしり」という呼び方だったが、この辺り(庄内地域)では「犬走り→いなはしり」と昔から言っているから、どこの建築やでもわがる!!とじいちゃん言い切る 。
。
由来は、犬が走れる幅しかない道という意味だそうです。
庄内弁に訛ったんかーい?
だったら広いものは「欽ちゃん走り」→欽ちゃんが走れる幅wwwと考えて、一人で肩を震わせましたが、
ホントは犬走りより広いものは「堧地(ぜんち)」というそうです。
建物のいなばしりは軒下に作り、構造物の保護を目的としています。
まずは「墨出し」で基礎に水平に線を付けるわけですが、墨だから黒色だろうと思ったら赤色だった
水平の線が付いたら、砂利を敷く高さを確保するため、少し基礎の周りを掘ってから、機械で圧をかけ平らにし、砂利を敷き又機械で圧をかけていきます。

そして基礎に穴をあけて鉄筋を挿して、いなばしりの補強していきます。
赤い色見えるかな?

そして、型枠を設置し、さらに鉄筋を渡してコンクリートを流す準備をします。

本日はここまで~
簡単に書いてますが、結構時間がかかるのですね。
冬でもお天気がいいとはかどりますのー
続きはまた後日~
本日は2月というのに暖かい陽気にめぐまれました

ちょっと手が空いたので、我が家のいなばしりを作成中。
前は「いなばしり=稲はしり」だと思っていたら、どうやら「犬走り」が本当の漢字ということが私の中で発覚

WIKIでは「犬走り→いぬはしり」という呼び方だったが、この辺り(庄内地域)では「犬走り→いなはしり」と昔から言っているから、どこの建築やでもわがる!!とじいちゃん言い切る
 。
。由来は、犬が走れる幅しかない道という意味だそうです。
庄内弁に訛ったんかーい?

だったら広いものは「欽ちゃん走り」→欽ちゃんが走れる幅wwwと考えて、一人で肩を震わせましたが、
ホントは犬走りより広いものは「堧地(ぜんち)」というそうです。
建物のいなばしりは軒下に作り、構造物の保護を目的としています。
まずは「墨出し」で基礎に水平に線を付けるわけですが、墨だから黒色だろうと思ったら赤色だった

水平の線が付いたら、砂利を敷く高さを確保するため、少し基礎の周りを掘ってから、機械で圧をかけ平らにし、砂利を敷き又機械で圧をかけていきます。

そして基礎に穴をあけて鉄筋を挿して、いなばしりの補強していきます。
赤い色見えるかな?

そして、型枠を設置し、さらに鉄筋を渡してコンクリートを流す準備をします。

本日はここまで~
簡単に書いてますが、結構時間がかかるのですね。
冬でもお天気がいいとはかどりますのー

続きはまた後日~

2016年02月06日
基礎もいろいろ♪
GOGO左官店にようこそ!
鶴岡はさむーい冬ですが、それでも住宅の基礎とかのご依頼があるんですよ~。
寒い時期の基礎はあまりお勧めしないのですが、最近は資材が発達し、凍結しないようにできるコンクリ素材などもあるので、科学の進歩は建築資材も進化できるのね~としみじみ
それはさておき、昨年作成したちょっと面白いお稲荷様の基礎の写真をアップ!

こちら我が家のお稲荷様です。
神様なので、石などで設置したほうが恰好よかったりするのですが、左官屋らしくコンクリートで大きく作成してみました。
石を貼るというパターンもありますが、結構いい金額になるので、石を重ねた風に型枠を作り、中に芯になる鉄筋を組んでコンクリートを流しいれてみました。
型を外せばこの通り!なんだか組石風基礎の完成
これが雨風で少しずつ風化し、苔なんか生えちゃったらさらに石ぽく見える!はず・・・
上に設置のお稲荷様ですが、石造りのお社です。
今まではコンクリートで自作のボロボロなお社だったので、「家が新しくなったのにうちらも新しくせんかい!! 」と思っているに違いない!!とお稲荷さんのお社も新調したのでした
」と思っているに違いない!!とお稲荷さんのお社も新調したのでした
ネットで探すと木で作ったお社が多く、石造りは石屋さん 例えば「〇〇石店」「石の〇〇」という店名のところでないと扱っていないのでした。
国産と中国産の石では価格も全く違うのでびっくり!
石もいろいろあるのですね~
まんず家の守り神ということもあり気合い入れて作ったので、地震があっても倒壊しないお稲荷様になりました
でもこの冬はばたばたして雪囲いしなかったので、来年はちゃんと雪囲いしなまねの。
雪国は、雪囲いしないとなんでも長持ちしないのでしたー
鶴岡はさむーい冬ですが、それでも住宅の基礎とかのご依頼があるんですよ~。
寒い時期の基礎はあまりお勧めしないのですが、最近は資材が発達し、凍結しないようにできるコンクリ素材などもあるので、科学の進歩は建築資材も進化できるのね~としみじみ

それはさておき、昨年作成したちょっと面白いお稲荷様の基礎の写真をアップ!

こちら我が家のお稲荷様です。
神様なので、石などで設置したほうが恰好よかったりするのですが、左官屋らしくコンクリートで大きく作成してみました。
石を貼るというパターンもありますが、結構いい金額になるので、石を重ねた風に型枠を作り、中に芯になる鉄筋を組んでコンクリートを流しいれてみました。
型を外せばこの通り!なんだか組石風基礎の完成

これが雨風で少しずつ風化し、苔なんか生えちゃったらさらに石ぽく見える!はず・・・
上に設置のお稲荷様ですが、石造りのお社です。
今まではコンクリートで自作のボロボロなお社だったので、「家が新しくなったのにうちらも新しくせんかい!!
 」と思っているに違いない!!とお稲荷さんのお社も新調したのでした
」と思っているに違いない!!とお稲荷さんのお社も新調したのでした
ネットで探すと木で作ったお社が多く、石造りは石屋さん 例えば「〇〇石店」「石の〇〇」という店名のところでないと扱っていないのでした。
国産と中国産の石では価格も全く違うのでびっくり!
石もいろいろあるのですね~

まんず家の守り神ということもあり気合い入れて作ったので、地震があっても倒壊しないお稲荷様になりました

でもこの冬はばたばたして雪囲いしなかったので、来年はちゃんと雪囲いしなまねの。
雪国は、雪囲いしないとなんでも長持ちしないのでしたー
2013年07月22日
花壇補修
GOGO左官店にようこそ!
今回は花壇補修の巻
花壇といってもいろんな花壇があるわけで、今回は面白い花壇の補修を行いました。
花壇といえば「レンガ」のイメージですが、大きな花壇を全部本物のレンガで作ってしまうと高額&補修費が高くなるので、「なんちゃってレンガ花壇」というのもあります(私がかってに着けたネーミングですが )。
)。
一体どんなものかというと・・・これです↓

思いっきり補修中の写真ですが、じつはコンクリートブロックで塀のように囲って花壇の基礎を作り、その周りにモルタルを塗って、薄いレンガ風タイルを張って作る方法です!実はこちらのほうが丈夫だったりします。
車が水道栓にぶつかり、そのまま花壇までつっきてしまったのですが、ブロックだったのと水道栓がワンクッションになったおかげで表のタイル張り部分の張替えで程度で済みました。
たぶんこれがレンガを積み上げた花壇だったら、一面全部に亀裂が入って、レンガ交換の積み直しになるところだと思います。
今回はその花壇の補修依頼を受けましたので、壊れた部分を崩し、新しくタイルを張って直します。
スカッと破損したタイルとブロック部分をキレイに取り除きました。

添え木をして、モルタルを重ねて平らにします。

水道栓も破損したので交換し、基礎部分も補修します。
乾燥したら、補修・接着液を塗布し、タイルを張り付けます。

しっかり接着したら、目地を埋めます。

そして濡れたスポンジでタイルに付いたモルタルを拭き取り完成です

これから花壇作成を考えている方、丈夫な花壇はこんな花壇をオススメしますよ~
今回は花壇補修の巻
花壇といってもいろんな花壇があるわけで、今回は面白い花壇の補修を行いました。
花壇といえば「レンガ」のイメージですが、大きな花壇を全部本物のレンガで作ってしまうと高額&補修費が高くなるので、「なんちゃってレンガ花壇」というのもあります(私がかってに着けたネーミングですが
 )。
)。一体どんなものかというと・・・これです↓

思いっきり補修中の写真ですが、じつはコンクリートブロックで塀のように囲って花壇の基礎を作り、その周りにモルタルを塗って、薄いレンガ風タイルを張って作る方法です!実はこちらのほうが丈夫だったりします。
車が水道栓にぶつかり、そのまま花壇までつっきてしまったのですが、ブロックだったのと水道栓がワンクッションになったおかげで表のタイル張り部分の張替えで程度で済みました。
たぶんこれがレンガを積み上げた花壇だったら、一面全部に亀裂が入って、レンガ交換の積み直しになるところだと思います。
今回はその花壇の補修依頼を受けましたので、壊れた部分を崩し、新しくタイルを張って直します。
スカッと破損したタイルとブロック部分をキレイに取り除きました。

添え木をして、モルタルを重ねて平らにします。

水道栓も破損したので交換し、基礎部分も補修します。

乾燥したら、補修・接着液を塗布し、タイルを張り付けます。

しっかり接着したら、目地を埋めます。

そして濡れたスポンジでタイルに付いたモルタルを拭き取り完成です


これから花壇作成を考えている方、丈夫な花壇はこんな花壇をオススメしますよ~

2013年06月27日
ブロック掃除
GOGO左官店にようこそ!
今日は「ブロック掃除」の巻。
また事故現場の復旧ですが、今回はブロック塀に付いたゴムの汚れを取るお仕事です。
一体どんなので取るかというと・・・なんと「ジフ」でした

ええ~と驚いた皆様 わたしもビックリです!
わたしもビックリです!
ですが、意外にキレイにとれる上に、しっかり洗浄しても何故か白い粉がブロックのザラザラした面に入り込んで、なんだかキレイに見えてしまうマジックが
大概の汚れはジフで最初に洗浄してみます。

早速ジフでゴシゴシ
それでもなかなかゴム汚れが落ちない時は、サンダーでちょっと削ったりもします。

ウィーン ガリガリ

デッキブラシでゴシゴシした後に高圧洗浄

じゃーん 完成です!
完成です!

キレイになりましたね~!
この夏、ブロックの汚れが目立って見えたら、洗ってみるのもいいかもしれませんよ
カムバック!綺麗な塀
今日は「ブロック掃除」の巻。
また事故現場の復旧ですが、今回はブロック塀に付いたゴムの汚れを取るお仕事です。
一体どんなので取るかというと・・・なんと「ジフ」でした


ええ~と驚いた皆様
 わたしもビックリです!
わたしもビックリです!
ですが、意外にキレイにとれる上に、しっかり洗浄しても何故か白い粉がブロックのザラザラした面に入り込んで、なんだかキレイに見えてしまうマジックが

大概の汚れはジフで最初に洗浄してみます。

早速ジフでゴシゴシ
それでもなかなかゴム汚れが落ちない時は、サンダーでちょっと削ったりもします。

ウィーン ガリガリ

デッキブラシでゴシゴシした後に高圧洗浄


じゃーん
 完成です!
完成です!
キレイになりましたね~!

この夏、ブロックの汚れが目立って見えたら、洗ってみるのもいいかもしれませんよ

カムバック!綺麗な塀

2013年04月30日
路面灯復旧工事
GOGO左官店にようこそ!
久しぶりに戻ってきました~!
道具の紹介しようと思いましたが、意外にも調べるのが難しいので、先に工事作業紹介に変更しました
さて、今回は温海温泉の道路にある路面灯の復旧作業です。
車にぶつけられて見事に壊れていますね~

まずは、先に街灯の枠を交換します。外灯等を直す時は、電気屋さんもお願いし、灯りがつくかどうかの作動確認も一緒に行います!確認OKが出てから、左官作業に入ります!

そして、コンクリート部分の補修。

ちょっと隙間があるので、板を挟め、真直ぐに塗れる様に添え木をします。
外灯枠の部分は隙間が無いので、コンクリートが付かない様に養生します。

こんな感じでキレイに塗りました。そして1日乾燥させます。

乾燥したら添え木を外し、仕上げの保護液を塗布して完成です!

こんな感じでよみがえりました
お家のコンクリート部分のちょっとした補修にも使えるので、添え木や養生などは、覚えておくと便利いいですよ!
久しぶりに戻ってきました~!
道具の紹介しようと思いましたが、意外にも調べるのが難しいので、先に工事作業紹介に変更しました

さて、今回は温海温泉の道路にある路面灯の復旧作業です。
車にぶつけられて見事に壊れていますね~


まずは、先に街灯の枠を交換します。外灯等を直す時は、電気屋さんもお願いし、灯りがつくかどうかの作動確認も一緒に行います!確認OKが出てから、左官作業に入ります!


そして、コンクリート部分の補修。

ちょっと隙間があるので、板を挟め、真直ぐに塗れる様に添え木をします。
外灯枠の部分は隙間が無いので、コンクリートが付かない様に養生します。

こんな感じでキレイに塗りました。そして1日乾燥させます。

乾燥したら添え木を外し、仕上げの保護液を塗布して完成です!

こんな感じでよみがえりました

お家のコンクリート部分のちょっとした補修にも使えるので、添え木や養生などは、覚えておくと便利いいですよ!

2013年02月21日
寒さに負けた・・・
GOGO左官店にようこそ!
今回は寒さに負けてしまったお話し。
最近暖かくなったり寒波襲来したりと両極端な冬ですが、先日から始まった寒波の中雪をかきわけて標識の支柱の交換工事を行いましたというか行うはずだったのです・・・
事故で破損した道路標識の支柱交換の為に現場に行きました。

曲がった支柱を交換するために、破損した支柱を根本から切断します。
そして、基礎に埋まった支柱を取り出すために、コア抜きという作業があります。

このような機械を使って、真ん中の太い筒がクルクル回転して堀下がっていくことにより、基礎をくり抜いていくのですが、なんと! 途中で凍って動かなくなってしまいました!
途中で凍って動かなくなってしまいました!
正確に言うと、この機械でくり抜いて行く作業の時に、かなりの摩擦が発生するので、熱と抵抗を減らすために水を流しながら作業を行うのですが、その水があまりの寒さにホースの途中で凍ってしまい、水が出ないので機械が動かなくなってしまったのでした
そんなことってあるんだー!!
水がでないと機械が動かず、コア抜きできなければ、支柱の交換も出来ず、そんなわけで遂に仕事を途中で断念して、諦めて帰って来てしまいました。
ウウウ まさか水が凍って工事できなくなるとは思いも寄らなかったです・・・
まさか水が凍って工事できなくなるとは思いも寄らなかったです・・・
寒さに負けた・・・。
やはり人間は自然に勝てないのですね。外作業は寒波の中行うべきではないですの・・・
今回は寒さに負けてしまったお話し。
最近暖かくなったり寒波襲来したりと両極端な冬ですが、先日から始まった寒波の中雪をかきわけて標識の支柱の交換工事を行いましたというか行うはずだったのです・・・

事故で破損した道路標識の支柱交換の為に現場に行きました。

曲がった支柱を交換するために、破損した支柱を根本から切断します。
そして、基礎に埋まった支柱を取り出すために、コア抜きという作業があります。

このような機械を使って、真ん中の太い筒がクルクル回転して堀下がっていくことにより、基礎をくり抜いていくのですが、なんと!
 途中で凍って動かなくなってしまいました!
途中で凍って動かなくなってしまいました!
正確に言うと、この機械でくり抜いて行く作業の時に、かなりの摩擦が発生するので、熱と抵抗を減らすために水を流しながら作業を行うのですが、その水があまりの寒さにホースの途中で凍ってしまい、水が出ないので機械が動かなくなってしまったのでした

そんなことってあるんだー!!
水がでないと機械が動かず、コア抜きできなければ、支柱の交換も出来ず、そんなわけで遂に仕事を途中で断念して、諦めて帰って来てしまいました。
ウウウ
 まさか水が凍って工事できなくなるとは思いも寄らなかったです・・・
まさか水が凍って工事できなくなるとは思いも寄らなかったです・・・寒さに負けた・・・。
やはり人間は自然に勝てないのですね。外作業は寒波の中行うべきではないですの・・・
2012年12月23日
車止めってどうやってくっついてるの?(コンクリート製だよ)
雪も降って、工事も大変になってきましたが、除雪機で車止めが破損してしまったということで、修理の依頼がやってきました!
しかし、ものの見事に欠けていたので、新規交換ということで施工。
これが新しく設置する車止めです

車止めといってもいろんな種類があるのですが、今回の車止めは「車がこれ以上後ろ(先)に進まないようにする」タイプで、壁などの前に設置するタイプです。
今回はガソリンスタンドに設置の車止めでしたが、やはり壁にぶつからないような場所に設置してありました。

初めは、元々あった個所をきれいに整えます。バーナーで、ごとごとした部分を焼いて平らにします。
そしてこれ

ボンド~
何で付けるのかなぁと思っていたら、こんなボンドで付けるんですね・・・なんだか意外
しかも、なんで車の絵?と思ったら、よく見たら車止めも・・・。車が目立ちすぎて一瞬判りませんでした もっと車止め目立たせようよ!!
もっと車止め目立たせようよ!!

ちゃんと付くようにいっぱい付けます(笑)。ほとんど1本まるごと使用。

そしてボンドの上に乗せたら、ボルトで固定。だよね~ ボンドだけかと思ってびっくりしたよ~
ボンドだけかと思ってびっくりしたよ~
↑の事を話したら、「んなわけねーだろ 」と主人にあきれられたww
」と主人にあきれられたww
いや、ホントにね、初心者なんで知らないんですよ・・・勉強中なんでハイ
そしてドリルで固定するのかと思えば、ハンマーで打ちつけてました

なんだかみごとに裏切られた気分・・・ ネジタイプじゃなかったのか・・・
ネジタイプじゃなかったのか・・・
ガンガン打ちつけていきます。

そしてボルト部分にプラスチックの蓋をして完成
車止めって意識したことなかったのですが、こんなふうに付いてたんだなぁ~とわかりました
ふう・・・きょうもいい勉強になったぜ
しかし、ものの見事に欠けていたので、新規交換ということで施工。
これが新しく設置する車止めです


車止めといってもいろんな種類があるのですが、今回の車止めは「車がこれ以上後ろ(先)に進まないようにする」タイプで、壁などの前に設置するタイプです。
今回はガソリンスタンドに設置の車止めでしたが、やはり壁にぶつからないような場所に設置してありました。

初めは、元々あった個所をきれいに整えます。バーナーで、ごとごとした部分を焼いて平らにします。
そしてこれ


ボンド~

何で付けるのかなぁと思っていたら、こんなボンドで付けるんですね・・・なんだか意外

しかも、なんで車の絵?と思ったら、よく見たら車止めも・・・。車が目立ちすぎて一瞬判りませんでした
 もっと車止め目立たせようよ!!
もっと車止め目立たせようよ!!
ちゃんと付くようにいっぱい付けます(笑)。ほとんど1本まるごと使用。

そしてボンドの上に乗せたら、ボルトで固定。だよね~
 ボンドだけかと思ってびっくりしたよ~
ボンドだけかと思ってびっくりしたよ~↑の事を話したら、「んなわけねーだろ
 」と主人にあきれられたww
」と主人にあきれられたwwいや、ホントにね、初心者なんで知らないんですよ・・・勉強中なんでハイ

そしてドリルで固定するのかと思えば、ハンマーで打ちつけてました


なんだかみごとに裏切られた気分・・・
 ネジタイプじゃなかったのか・・・
ネジタイプじゃなかったのか・・・ガンガン打ちつけていきます。

そしてボルト部分にプラスチックの蓋をして完成
車止めって意識したことなかったのですが、こんなふうに付いてたんだなぁ~とわかりました

ふう・・・きょうもいい勉強になったぜ

2012年11月24日
月の型抜き!
ご無沙汰です~菅原左官店です
今日は朝からいろんな用事を済まし、夕方家に帰ってきたら、事務所の脇の小部屋で何やら面白そうなことをしていたのを発見

「何作ってんな~?」
「壁~」
見りゃわかるけど、あまり会話になっていないような・・・・
集中して塗っているのに声かけてすみません
しまった!!一日いないせいで、最初から写真とれなかった!と後悔
後から社長(義父)に聞くと、ワタナベエンタープライズ様からのご依頼で、鶴岡駅前の「月の王様」さまの仕切り壁を作成しているとのこと。
月の形の抜型だったので、もしかしたら?と思っていたら直感が当たってました(笑)
月の形は、大工さんが発砲スチロールで作ってくれて、それを壁の基礎にはめ込み作成したとのこと。
おお~面白い~
こちらはきれいに仕上げた面です。これから最終仕上げに入るそうです。

素材は珪藻土でぬり上げております!飲み屋さんは、たばこやアルコールなどいろんな香りがするので、吸着しやすい(けっこう消臭効果あり)の珪藻土使用のほうが一石二鳥な感じで、出来上がりもいい感じです~
月曜日納品とのことで、今日は一晩中ストーブを付けて乾燥させます。何だか危ない感じだけど、今時期は普通にしていても乾燥しないのでしょうがないのです。
あとは倒れないようにしないといけないので、大きな地震が無いことを願います
もし「月の王様」さまにいって、この壁を発見したときは、「羽黒の菅原左官店作ったっけの~ 」と思い出してくれたらありがたいデスの
」と思い出してくれたらありがたいデスの

今日は朝からいろんな用事を済まし、夕方家に帰ってきたら、事務所の脇の小部屋で何やら面白そうなことをしていたのを発見


「何作ってんな~?」
「壁~」
見りゃわかるけど、あまり会話になっていないような・・・・

集中して塗っているのに声かけてすみません

しまった!!一日いないせいで、最初から写真とれなかった!と後悔

後から社長(義父)に聞くと、ワタナベエンタープライズ様からのご依頼で、鶴岡駅前の「月の王様」さまの仕切り壁を作成しているとのこと。
月の形の抜型だったので、もしかしたら?と思っていたら直感が当たってました(笑)

月の形は、大工さんが発砲スチロールで作ってくれて、それを壁の基礎にはめ込み作成したとのこと。
おお~面白い~

こちらはきれいに仕上げた面です。これから最終仕上げに入るそうです。

素材は珪藻土でぬり上げております!飲み屋さんは、たばこやアルコールなどいろんな香りがするので、吸着しやすい(けっこう消臭効果あり)の珪藻土使用のほうが一石二鳥な感じで、出来上がりもいい感じです~

月曜日納品とのことで、今日は一晩中ストーブを付けて乾燥させます。何だか危ない感じだけど、今時期は普通にしていても乾燥しないのでしょうがないのです。
あとは倒れないようにしないといけないので、大きな地震が無いことを願います

もし「月の王様」さまにいって、この壁を発見したときは、「羽黒の菅原左官店作ったっけの~
 」と思い出してくれたらありがたいデスの
」と思い出してくれたらありがたいデスの
2012年11月17日
門の欠けた所直しだよ!
先日入口の門がかけたので、みっともないから直してくれ~ とのご依頼があり、早速直してきました!
とのご依頼があり、早速直してきました!
ちなみにこんな感じの欠けっぷりです

トラックが曲がりきれなくてぶつかってしまったそうです
どうやって復旧するかというと・・・

まずはモルタル補修液を欠けた箇所に塗りぬり。これを塗らないですぐコンクリート塗ると、時間が経つとポロリと落ちてきます ww
ww
両わきに添え木をして型枠にし、塗っていきます!

そしてしばらく乾かして、表面が乾いてきたら、型枠を取り除き完成です
脇などもキレイにならして完成



キレイになりましたね~
入口の欠けは運気が欠けるとのことで、商売している方は嫌いますので、ビシッと直って依頼主様もゆっくりした~と喜んで頂きました
年末にあたり、気になる所がありましたらスッキリ直して、新年を迎えてみてはいかがですか~
 とのご依頼があり、早速直してきました!
とのご依頼があり、早速直してきました!ちなみにこんな感じの欠けっぷりです

トラックが曲がりきれなくてぶつかってしまったそうです

どうやって復旧するかというと・・・

まずはモルタル補修液を欠けた箇所に塗りぬり。これを塗らないですぐコンクリート塗ると、時間が経つとポロリと落ちてきます
 ww
ww両わきに添え木をして型枠にし、塗っていきます!

そしてしばらく乾かして、表面が乾いてきたら、型枠を取り除き完成です

脇などもキレイにならして完成




キレイになりましたね~

入口の欠けは運気が欠けるとのことで、商売している方は嫌いますので、ビシッと直って依頼主様もゆっくりした~と喜んで頂きました

年末にあたり、気になる所がありましたらスッキリ直して、新年を迎えてみてはいかがですか~

2012年11月06日
ブロック塀復旧工事 その3
睡魔に襲われて その2があっという間でしたが、今回最終回です
その2があっという間でしたが、今回最終回です
4日目のブロック積み ちなみにこのブロックは石でできています

一つひとつ丁寧に設置していきます。結構重いのですが、慣れたもので着々とのせていくので力持ちだな~と思います
5日目、4日目の続きでブロックを積み、最後の一番上には笠を乗せます。「笠」とは、ちっちゃいブロックの事をいいます。
これで塀の善し悪しが決まったりするので、大きなブロックを積む以上に気を使うそうです。

そして基礎の部分をキレイに化粧塗りします。前面を均一に美しく仕上げるところに、職人技がひかります

そして一晩乾燥させます。
6日目。足元をキレイにならします。

台をのせたりしているので、意外に凹みがあったりしていますので、忘れずに化粧塗りします。
そして完成~

門も直したい所ですが、事故で壊れた部分のみの依頼だったので、このような仕上がりです。
しかし、石ブロックでの塀は高級なので、なかなか依頼がないお仕事なので、きちっと撮影できて良かったです。またこのようなお仕事あったらアップしたいと思いま~す
 その2があっという間でしたが、今回最終回です
その2があっという間でしたが、今回最終回です
4日目のブロック積み ちなみにこのブロックは石でできています


一つひとつ丁寧に設置していきます。結構重いのですが、慣れたもので着々とのせていくので力持ちだな~と思います

5日目、4日目の続きでブロックを積み、最後の一番上には笠を乗せます。「笠」とは、ちっちゃいブロックの事をいいます。
これで塀の善し悪しが決まったりするので、大きなブロックを積む以上に気を使うそうです。

そして基礎の部分をキレイに化粧塗りします。前面を均一に美しく仕上げるところに、職人技がひかります


そして一晩乾燥させます。
6日目。足元をキレイにならします。

台をのせたりしているので、意外に凹みがあったりしていますので、忘れずに化粧塗りします。
そして完成~


門も直したい所ですが、事故で壊れた部分のみの依頼だったので、このような仕上がりです。
しかし、石ブロックでの塀は高級なので、なかなか依頼がないお仕事なので、きちっと撮影できて良かったです。またこのようなお仕事あったらアップしたいと思いま~す

2012年11月05日
ブロック塀復旧工事 その2
さて、通うこと3日目。いよいよブロックを乗せる基礎を作成。
まずは、型枠を作ります。ここの部分にもしっかり鉄筋を入れて補強します。

そしコンクリートを流しいれ、またしても1日乾燥。
4日目、型を外し、水平確認のためテグスを設置します。

これからようやくブロックを積んでいきます。
大きなブロックで、ずれると修正が大変なので、一つ一つ丁寧につんでいきます。

次は2段目です。けっこうちゃっちゃと出来そうなイメージですが、重たいのでなかなかたいへんです
その3につづく
まずは、型枠を作ります。ここの部分にもしっかり鉄筋を入れて補強します。

そしコンクリートを流しいれ、またしても1日乾燥。
4日目、型を外し、水平確認のためテグスを設置します。

これからようやくブロックを積んでいきます。
大きなブロックで、ずれると修正が大変なので、一つ一つ丁寧につんでいきます。

次は2段目です。けっこうちゃっちゃと出来そうなイメージですが、重たいのでなかなかたいへんです

その3につづく
2012年11月01日
ブロック塀復旧工事その1
今回は左官屋さん得意のお仕事がありました~
場所は最上町です(ちょっと遠いですが )結構大きな工事だったので、6日間通って施工いたしました!
)結構大きな工事だったので、6日間通って施工いたしました!
珍しく立派なブロック塀の工事なので、写真で説明しまーす
1日目、まずは既存のブロックを撤去し、植木の移動を行いました。樹木は傷つけないように手作業で移動だったので、大変でした。

2日目、撤去したブロックの場所に新たに基礎を作る為、地ならしをして調整します。

そして基礎となる鉄筋を設置。

コンクリートを流しいれて、基礎をつくります。最終仕上げがきれいになるように、今からきちんとぬります。

そして、乾かしておきます!

コーンを立てて注意をうながし、踏まれないようにしますが、猫や鳥には関係なく・・・
内陸は結構天気がいいので助かりますな~
きちんと乾燥させないでブロックをのせると、基礎が沈んでしますので(今回のブロックは重いので)、きっちり乾くまで3日おきました 。
。
その2へつづく

場所は最上町です(ちょっと遠いですが
 )結構大きな工事だったので、6日間通って施工いたしました!
)結構大きな工事だったので、6日間通って施工いたしました!珍しく立派なブロック塀の工事なので、写真で説明しまーす

1日目、まずは既存のブロックを撤去し、植木の移動を行いました。樹木は傷つけないように手作業で移動だったので、大変でした。

2日目、撤去したブロックの場所に新たに基礎を作る為、地ならしをして調整します。

そして基礎となる鉄筋を設置。

コンクリートを流しいれて、基礎をつくります。最終仕上げがきれいになるように、今からきちんとぬります。

そして、乾かしておきます!

コーンを立てて注意をうながし、踏まれないようにしますが、猫や鳥には関係なく・・・
内陸は結構天気がいいので助かりますな~

きちんと乾燥させないでブロックをのせると、基礎が沈んでしますので(今回のブロックは重いので)、きっちり乾くまで3日おきました
 。
。その2へつづく
2012年10月25日
文化伝統と技術を伝える意義
お仕事アップ!というか、写真整理をしていたら、面白い写真が出てきたので書いてみました。
最近民家を建設する際の左官業といえば、基礎工事・玄関ポーチのタイルやコンクリート・ブロック塀・お風呂のタイル貼り(最近めっきり少ないですけど )などがありますが、一番の腕の魅せどころは「壁塗り」なんです。
)などがありますが、一番の腕の魅せどころは「壁塗り」なんです。
左官屋と言いながら、壁塗り出来ない職人さんもおりますので、「壁塗り」は本当に技術がいるものなのです
しかし、白壁の家なんて最近ほとんどなく、なかなか技術を継承する場が無いのが問題です。
そして究極の壁塗りは「土壁」です。
また、壁を塗ることは出来ても、土壁をイチから作れる方が段々減ってきて、この鶴岡市内では3人ほどしかおらず、現役の左官職人ではわが社の社長(義父)だけなのだそうです。
現在庄内には土壁に適した粘土状の土がないので、新潟に仕入れに行きます。
土をこねる際も、硬さやわらの配合など、口で言ってもわからない感覚的なものがあるので、やり方を見て覚えるしか無いのです。
壁の下地には「木舞(こまい)」というものを使いますが、この木舞のを作るときの結び方や幅などは全国の地域によって違い、庄内もまた違うのでした。その風土気候に合わせた独自の方法があるのです。
この写真は、ずいぶん前になりますが、羽黒で土壁の建物を建てるときに、唯一の職人として先生になって欲しいと依頼を受けて、一般の人に木舞の作り方を指導している時のものです。ちなみに、木舞を作るのを「こめかき」といいます。庄内弁だと「こめがぎ」と濁点で言いますww

珍しいので、テレビ局からも取材を受けました
そして社長のほかにも助っ人で、第一線を退いた師匠も来ていただき、うちの職人さんにも指導して頂きました。

土だけだと長持ちしないので、ちょっと現代の素材を入れて長寿命化したりと、きちんと技術を継承しているからこそ出来るアレンジもあるのでした 。
。
なかなかこのような機会がないので、従業員のみんなも大変勉強になりましが、この時私はまだお手伝いもしていなかったので、貴重なデーターを撮る事ができませんでした
技術を知っていても継承できる機会が全くないので、歴史と文化を引き継ぐ為にも、このようなお仕事があればなあ・・・ と最近しみじみ思います。
と最近しみじみ思います。
どんなに良いものでも、必要性がなければ消滅してしまうのか・・・
社長が生きているうちに、もう一度このような機会があったら、今度はイチから十まで撮影&レポートにし、後世に伝承できるようにしていきたいと思ってます。
鶴岡市に鶴ケ岡城でも復活したら、大活躍できるんだろうな・・・ww
最近民家を建設する際の左官業といえば、基礎工事・玄関ポーチのタイルやコンクリート・ブロック塀・お風呂のタイル貼り(最近めっきり少ないですけど
 )などがありますが、一番の腕の魅せどころは「壁塗り」なんです。
)などがありますが、一番の腕の魅せどころは「壁塗り」なんです。左官屋と言いながら、壁塗り出来ない職人さんもおりますので、「壁塗り」は本当に技術がいるものなのです

しかし、白壁の家なんて最近ほとんどなく、なかなか技術を継承する場が無いのが問題です。
そして究極の壁塗りは「土壁」です。
また、壁を塗ることは出来ても、土壁をイチから作れる方が段々減ってきて、この鶴岡市内では3人ほどしかおらず、現役の左官職人ではわが社の社長(義父)だけなのだそうです。
現在庄内には土壁に適した粘土状の土がないので、新潟に仕入れに行きます。
土をこねる際も、硬さやわらの配合など、口で言ってもわからない感覚的なものがあるので、やり方を見て覚えるしか無いのです。
壁の下地には「木舞(こまい)」というものを使いますが、この木舞のを作るときの結び方や幅などは全国の地域によって違い、庄内もまた違うのでした。その風土気候に合わせた独自の方法があるのです。
この写真は、ずいぶん前になりますが、羽黒で土壁の建物を建てるときに、唯一の職人として先生になって欲しいと依頼を受けて、一般の人に木舞の作り方を指導している時のものです。ちなみに、木舞を作るのを「こめかき」といいます。庄内弁だと「こめがぎ」と濁点で言いますww


珍しいので、テレビ局からも取材を受けました

そして社長のほかにも助っ人で、第一線を退いた師匠も来ていただき、うちの職人さんにも指導して頂きました。

土だけだと長持ちしないので、ちょっと現代の素材を入れて長寿命化したりと、きちんと技術を継承しているからこそ出来るアレンジもあるのでした
 。
。なかなかこのような機会がないので、従業員のみんなも大変勉強になりましが、この時私はまだお手伝いもしていなかったので、貴重なデーターを撮る事ができませんでした

技術を知っていても継承できる機会が全くないので、歴史と文化を引き継ぐ為にも、このようなお仕事があればなあ・・・
 と最近しみじみ思います。
と最近しみじみ思います。どんなに良いものでも、必要性がなければ消滅してしまうのか・・・
社長が生きているうちに、もう一度このような機会があったら、今度はイチから十まで撮影&レポートにし、後世に伝承できるようにしていきたいと思ってます。
鶴岡市に鶴ケ岡城でも復活したら、大活躍できるんだろうな・・・ww

2012年10月08日
予想外のガラス拾いに悪戦苦闘
ちょっと真面目にお仕事のお話し。
「8日に仕事してください」と指定されていたのに、うっかり忘れていた社長 。午前中のメールチェックでその連絡メールを発見し、慌てて3人で松山の現場にGO
。午前中のメールチェックでその連絡メールを発見し、慌てて3人で松山の現場にGO !
!
現場を見るなり、あまりのガラスの飛散ぶりにガックリ・・・ 。
。

まさかこんなにガラスが粉々とは思っていなかったので、びっくりしました。
一体何時間かかるんだ?と思ったものの、黙々と拾いました。
薄手のゴム手袋していたのですが、1枚ではゴムを突き抜けてガラスがチクチク手に刺さるので、2枚重ね。

土の割れ目に潜り込んでいたり、稲の根元に紛れ込んでいたり、くいがけの周りにもガラスが飛び散っていたので、稲のなかにあったら大変と、隈なく丁寧に破片探し。
ドライバーで溝からかき出したり、スコップで土を掘り出して選別したりと、お昼も食べずに3時間半かかって、全て手作業で拾い集めました 。
。

これで、来年も土に影響なく稲作が出来るかな?
田んぼの事を考えると手を抜けないので、キッチリ拾ってきました!
また美味しいお米ができますように

「8日に仕事してください」と指定されていたのに、うっかり忘れていた社長
 。午前中のメールチェックでその連絡メールを発見し、慌てて3人で松山の現場にGO
。午前中のメールチェックでその連絡メールを発見し、慌てて3人で松山の現場にGO !
!現場を見るなり、あまりのガラスの飛散ぶりにガックリ・・・
 。
。
まさかこんなにガラスが粉々とは思っていなかったので、びっくりしました。
一体何時間かかるんだ?と思ったものの、黙々と拾いました。
薄手のゴム手袋していたのですが、1枚ではゴムを突き抜けてガラスがチクチク手に刺さるので、2枚重ね。

土の割れ目に潜り込んでいたり、稲の根元に紛れ込んでいたり、くいがけの周りにもガラスが飛び散っていたので、稲のなかにあったら大変と、隈なく丁寧に破片探し。
ドライバーで溝からかき出したり、スコップで土を掘り出して選別したりと、お昼も食べずに3時間半かかって、全て手作業で拾い集めました
 。
。
これで、来年も土に影響なく稲作が出来るかな?
田んぼの事を考えると手を抜けないので、キッチリ拾ってきました!
また美味しいお米ができますように


2012年09月21日
銀色のガードレールは注意の証し~
最近異様な忙しさに心の余裕がなく、ブログまで手が回らずしばらくお休みしておりましたが、ちょっと自分落ち着きが戻りつつあるので、久々にアップです~
最近海沿いのガードレールの工事をしました。
事故で破損したガードレールの交換工事です

このあたりは昔から事故が多い所のようで、白いガードレールには黄色の反射シールも付いていて、警戒を促しているのですが、どうも効果が・・・

というわけで、交換するにあたり、遂に白→銀色のガードレールになってしまいました

前に白以外のガードレールは気をつける場所なんだよ~と書きましたが、ここも危険箇所に認定されたのかな?元々は白だったのだけど、交換部品で来たのは銀色。
ここにガードレールがあるんだぞ!と自己主張しております
銀色に光って、夜でもハッキリ見えるようになるかもね。
落ち着いたら白に塗装とかされるのかしら?
緩いカーブの先の場所ではありますが、やはりスピードの出しすぎや無茶な運転はやめて、安全運転を心がけて頂きたいですね~

最近海沿いのガードレールの工事をしました。
事故で破損したガードレールの交換工事です


このあたりは昔から事故が多い所のようで、白いガードレールには黄色の反射シールも付いていて、警戒を促しているのですが、どうも効果が・・・


というわけで、交換するにあたり、遂に白→銀色のガードレールになってしまいました


前に白以外のガードレールは気をつける場所なんだよ~と書きましたが、ここも危険箇所に認定されたのかな?元々は白だったのだけど、交換部品で来たのは銀色。
ここにガードレールがあるんだぞ!と自己主張しております

銀色に光って、夜でもハッキリ見えるようになるかもね。
落ち着いたら白に塗装とかされるのかしら?
緩いカーブの先の場所ではありますが、やはりスピードの出しすぎや無茶な運転はやめて、安全運転を心がけて頂きたいですね~

2012年09月15日
映画村でのお仕事での出来事
面白ネタ。これは映画村のセットを作った時、土壁塗り依頼があり、お手伝いしたときの写真です!
わが左官店の職人が何人か行きましたが、この民家の壁は「あまり裕福でない民家の土壁」というコンセプトだったので、
スタッフ「もっとボロイ感じで塗ってください!」
職人「ボロくですか?」
ぬりぬり・・・
スタッフ「いやもっとみすぼらしく!」
...職人「ええッツ(゚∀゚)?」
仕事から帰ってきて、興味津々の私は「どうだった~?ww」と聞いたら、職人さん「下手くそに塗るのが難しかった・・・(-_-;)」
とぼそり。
プロの職人さんへの「下手くそに塗って!」という無茶ぶりなお願いに四苦八苦して塗ってきたとのことww
未だにわが社の語りぐさになってます・・・。

わが左官店の職人が何人か行きましたが、この民家の壁は「あまり裕福でない民家の土壁」というコンセプトだったので、
スタッフ「もっとボロイ感じで塗ってください!」
職人「ボロくですか?」
ぬりぬり・・・
スタッフ「いやもっとみすぼらしく!」
...職人「ええッツ(゚∀゚)?」
仕事から帰ってきて、興味津々の私は「どうだった~?ww」と聞いたら、職人さん「下手くそに塗るのが難しかった・・・(-_-;)」
とぼそり。
プロの職人さんへの「下手くそに塗って!」という無茶ぶりなお願いに四苦八苦して塗ってきたとのことww
未だにわが社の語りぐさになってます・・・。

2012年08月29日
トムとジェリーのチーズのような空気穴・・・
先日ふと我が家の門を見ていたら、側溝の壁がおかしなことになっていたのに気が付いた。
私が嫁に来てから、塀を一度補修したのだけど、その時の仕事ぶりの結果がこれだ!

分かりにくいので、拡大写真

壁画彫刻のような、トムとジェリーのチーズのような空気穴が多数・・・
確かこのときは新入社員の若い子に、練習といってさせていたような気が・・・
前々回に擁壁やら土留めコンクリートの写真をアップしてました。その中で、型枠の中でコンクリートを撹拌してましたが、その撹拌をしないと上記のような写真の結果になるのですよ。
型にただコンクリートを流しいれただけでは、場所によっては空気の塊のせいで、表面的にはまんべんなく流しいれた風にみえるときもあるのです。又はきちんと流しいれ切らない状態があのような空気の塊の状態で凝固してしまうのです。
そう!それはまさにシフォンケーキを切ってみたら、空気の穴があいていて、トムとジェリーのチーズのような焼き上がり という残念感にそっくり。
という残念感にそっくり。
シフォンケーキだって生地を流しいれたら、箸でぐるぐる回して空気抜くのと同じ作業を型枠でも行うのです。
擁壁や型枠の幅が大きい場合はあまりこんなことにはならないのですが、幅が狭いと写真のようなことになりやすいので、かえって難しい作業になるのですよ~。
まあこの側溝の場合は、2センチ幅の隙間のような型枠だったし、練習とその結果を身を以て体験した証ということですかね?
ここを見るたびに、「あー俺って・・・・」と思って戒めになっているかも 。
。
やはり、初めはみんなこんな感じだったということですね。論より証拠的な写真でした 。
。
そんな彼も今では現場を任せられる立派な職人さんに成長しました
私が嫁に来てから、塀を一度補修したのだけど、その時の仕事ぶりの結果がこれだ!

分かりにくいので、拡大写真


壁画彫刻のような、トムとジェリーのチーズのような空気穴が多数・・・

確かこのときは新入社員の若い子に、練習といってさせていたような気が・・・

前々回に擁壁やら土留めコンクリートの写真をアップしてました。その中で、型枠の中でコンクリートを撹拌してましたが、その撹拌をしないと上記のような写真の結果になるのですよ。
型にただコンクリートを流しいれただけでは、場所によっては空気の塊のせいで、表面的にはまんべんなく流しいれた風にみえるときもあるのです。又はきちんと流しいれ切らない状態があのような空気の塊の状態で凝固してしまうのです。
そう!それはまさにシフォンケーキを切ってみたら、空気の穴があいていて、トムとジェリーのチーズのような焼き上がり
 という残念感にそっくり。
という残念感にそっくり。シフォンケーキだって生地を流しいれたら、箸でぐるぐる回して空気抜くのと同じ作業を型枠でも行うのです。
擁壁や型枠の幅が大きい場合はあまりこんなことにはならないのですが、幅が狭いと写真のようなことになりやすいので、かえって難しい作業になるのですよ~。
まあこの側溝の場合は、2センチ幅の隙間のような型枠だったし、練習とその結果を身を以て体験した証ということですかね?
ここを見るたびに、「あー俺って・・・・」と思って戒めになっているかも
 。
。やはり、初めはみんなこんな感じだったということですね。論より証拠的な写真でした
 。
。そんな彼も今では現場を任せられる立派な職人さんに成長しました

2012年08月23日
土留コンクリート
前回は擁壁工事でしたが、今回は土留コンクリート新規打設です
土が流出しないように、コンクリートで土留をするので、またまた型枠を作成します。


今回は幅と長さがあるので、型枠の中でスクリューを回し、隙間が出来ないようまんべんなく撹拌しながらコンクリートを詰めていきます。

上をキレイになでていきます。

 なめらかで綺麗でしょう~
なめらかで綺麗でしょう~
このまま5日間完全に乾かします!

5日後キレイに乾燥しました!

型を外すとこんな感じの仕上がりです。ネジ穴が丸く空いてますの

穴をコンクリートで埋めて、下のコンクリートに流れた部分をキレイにしたら完成

ここで気がついたのだが、前回の擁壁より今回の方が擁壁っぽくない?と思って調べてみたら、「擁壁は土留と称される事もある」のだそうです。
擁壁の定義は、「宅地の土砂が崩壊するのを防ぐため、切土や盛土などの崖面を支える構造物」なのだそうですが、
「擁壁」は、本格的で長期的な構造
「土留」は、簡素で一時的な構造 というわけ方のようです。
フムフム なるほど!そうなると今回は土留のほうがバッチリ合いますね!
なるほど!そうなると今回は土留のほうがバッチリ合いますね!
前回の擁壁はちょっと違うような・・・・
まあこれからジャンル分け出来るようにもっと勉強だの

土が流出しないように、コンクリートで土留をするので、またまた型枠を作成します。


今回は幅と長さがあるので、型枠の中でスクリューを回し、隙間が出来ないようまんべんなく撹拌しながらコンクリートを詰めていきます。

上をキレイになでていきます。

 なめらかで綺麗でしょう~
なめらかで綺麗でしょう~
このまま5日間完全に乾かします!

5日後キレイに乾燥しました!


型を外すとこんな感じの仕上がりです。ネジ穴が丸く空いてますの


穴をコンクリートで埋めて、下のコンクリートに流れた部分をキレイにしたら完成


ここで気がついたのだが、前回の擁壁より今回の方が擁壁っぽくない?と思って調べてみたら、「擁壁は土留と称される事もある」のだそうです。
擁壁の定義は、「宅地の土砂が崩壊するのを防ぐため、切土や盛土などの崖面を支える構造物」なのだそうですが、
「擁壁」は、本格的で長期的な構造
「土留」は、簡素で一時的な構造 というわけ方のようです。
フムフム
 なるほど!そうなると今回は土留のほうがバッチリ合いますね!
なるほど!そうなると今回は土留のほうがバッチリ合いますね!前回の擁壁はちょっと違うような・・・・

まあこれからジャンル分け出来るようにもっと勉強だの

2012年08月22日
ミニ擁壁復旧工事
 久々に左官店らしい工事がありました
久々に左官店らしい工事がありました
駐車場の境界のコンクリート復旧です!「境界のコンクリート」と私はずっと思っていたのですが、「擁壁」という言葉を使っての依頼で、「これも擁壁ってジャンルなの
 ?」と初めて知りました・・・
?」と初めて知りました・・・擁壁って大きいコンクリートの壁のイメージだったのでビックリ

擁壁も大小様々なのね~ということで、わたし的に勝手に「ミニ擁壁」と名づけましたww
はて、今回は車でぶつけて壊してしまったとのことで、復旧するためにいったんキレイに撤去します。




大きいと持ち運び大変なので、細かく粉砕します。産業廃棄物で出すときもラクラクです

 キレイに片付けて、もともとの鉄筋を出しました。
キレイに片付けて、もともとの鉄筋を出しました。ちょっと間隔が大きいので、ドリルで穴を開けて鉄筋を足して補強します。


中の鉄筋骨組み完成

今度は型枠を作成し、コンクリートを流し込みます。


この型枠も、キレイに元の擁壁と合わせるためにも結構技術が必要なんですね。手先の器用さを求められます

固めのコンクリートを入れたら、滑らかなコンクリートを上から流し入れて整えます。

この状態で4日ほどおき、完全に乾かします。
 型を外しました
型を外しました しっかり固まっております!
しっかり固まっております!

表面をキレイにならして完成です

鉄筋が出たまんまですが、これはこの上に塀を作る際に必要なので、元の状態と同じように復旧した結果です。
ミニ擁壁、前よりは鉄筋の本数が増えているので、より丈夫になったはず・・・
復旧するにも時間とお金がかかるので、壊さないように運転は気を付けてしないといけませんの~