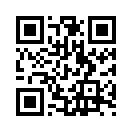2012年10月25日
文化伝統と技術を伝える意義
お仕事アップ!というか、写真整理をしていたら、面白い写真が出てきたので書いてみました。
最近民家を建設する際の左官業といえば、基礎工事・玄関ポーチのタイルやコンクリート・ブロック塀・お風呂のタイル貼り(最近めっきり少ないですけど )などがありますが、一番の腕の魅せどころは「壁塗り」なんです。
)などがありますが、一番の腕の魅せどころは「壁塗り」なんです。
左官屋と言いながら、壁塗り出来ない職人さんもおりますので、「壁塗り」は本当に技術がいるものなのです
しかし、白壁の家なんて最近ほとんどなく、なかなか技術を継承する場が無いのが問題です。
そして究極の壁塗りは「土壁」です。
また、壁を塗ることは出来ても、土壁をイチから作れる方が段々減ってきて、この鶴岡市内では3人ほどしかおらず、現役の左官職人ではわが社の社長(義父)だけなのだそうです。
現在庄内には土壁に適した粘土状の土がないので、新潟に仕入れに行きます。
土をこねる際も、硬さやわらの配合など、口で言ってもわからない感覚的なものがあるので、やり方を見て覚えるしか無いのです。
壁の下地には「木舞(こまい)」というものを使いますが、この木舞のを作るときの結び方や幅などは全国の地域によって違い、庄内もまた違うのでした。その風土気候に合わせた独自の方法があるのです。
この写真は、ずいぶん前になりますが、羽黒で土壁の建物を建てるときに、唯一の職人として先生になって欲しいと依頼を受けて、一般の人に木舞の作り方を指導している時のものです。ちなみに、木舞を作るのを「こめかき」といいます。庄内弁だと「こめがぎ」と濁点で言いますww

珍しいので、テレビ局からも取材を受けました
そして社長のほかにも助っ人で、第一線を退いた師匠も来ていただき、うちの職人さんにも指導して頂きました。

土だけだと長持ちしないので、ちょっと現代の素材を入れて長寿命化したりと、きちんと技術を継承しているからこそ出来るアレンジもあるのでした 。
。
なかなかこのような機会がないので、従業員のみんなも大変勉強になりましが、この時私はまだお手伝いもしていなかったので、貴重なデーターを撮る事ができませんでした
技術を知っていても継承できる機会が全くないので、歴史と文化を引き継ぐ為にも、このようなお仕事があればなあ・・・ と最近しみじみ思います。
と最近しみじみ思います。
どんなに良いものでも、必要性がなければ消滅してしまうのか・・・
社長が生きているうちに、もう一度このような機会があったら、今度はイチから十まで撮影&レポートにし、後世に伝承できるようにしていきたいと思ってます。
鶴岡市に鶴ケ岡城でも復活したら、大活躍できるんだろうな・・・ww
最近民家を建設する際の左官業といえば、基礎工事・玄関ポーチのタイルやコンクリート・ブロック塀・お風呂のタイル貼り(最近めっきり少ないですけど
 )などがありますが、一番の腕の魅せどころは「壁塗り」なんです。
)などがありますが、一番の腕の魅せどころは「壁塗り」なんです。左官屋と言いながら、壁塗り出来ない職人さんもおりますので、「壁塗り」は本当に技術がいるものなのです

しかし、白壁の家なんて最近ほとんどなく、なかなか技術を継承する場が無いのが問題です。
そして究極の壁塗りは「土壁」です。
また、壁を塗ることは出来ても、土壁をイチから作れる方が段々減ってきて、この鶴岡市内では3人ほどしかおらず、現役の左官職人ではわが社の社長(義父)だけなのだそうです。
現在庄内には土壁に適した粘土状の土がないので、新潟に仕入れに行きます。
土をこねる際も、硬さやわらの配合など、口で言ってもわからない感覚的なものがあるので、やり方を見て覚えるしか無いのです。
壁の下地には「木舞(こまい)」というものを使いますが、この木舞のを作るときの結び方や幅などは全国の地域によって違い、庄内もまた違うのでした。その風土気候に合わせた独自の方法があるのです。
この写真は、ずいぶん前になりますが、羽黒で土壁の建物を建てるときに、唯一の職人として先生になって欲しいと依頼を受けて、一般の人に木舞の作り方を指導している時のものです。ちなみに、木舞を作るのを「こめかき」といいます。庄内弁だと「こめがぎ」と濁点で言いますww


珍しいので、テレビ局からも取材を受けました

そして社長のほかにも助っ人で、第一線を退いた師匠も来ていただき、うちの職人さんにも指導して頂きました。

土だけだと長持ちしないので、ちょっと現代の素材を入れて長寿命化したりと、きちんと技術を継承しているからこそ出来るアレンジもあるのでした
 。
。なかなかこのような機会がないので、従業員のみんなも大変勉強になりましが、この時私はまだお手伝いもしていなかったので、貴重なデーターを撮る事ができませんでした

技術を知っていても継承できる機会が全くないので、歴史と文化を引き継ぐ為にも、このようなお仕事があればなあ・・・
 と最近しみじみ思います。
と最近しみじみ思います。どんなに良いものでも、必要性がなければ消滅してしまうのか・・・
社長が生きているうちに、もう一度このような機会があったら、今度はイチから十まで撮影&レポートにし、後世に伝承できるようにしていきたいと思ってます。
鶴岡市に鶴ケ岡城でも復活したら、大活躍できるんだろうな・・・ww

Posted by のりえもん at 18:05│Comments(0)
│工事