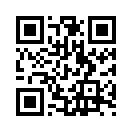2012年10月28日
子供会&地域行事こらぼ
10月の日曜はイベントが盛りだくさんですが、最終日曜日は地域行事で〆ました
まずは朝7時集合で、地域の皆さんと子供会でクリーン作戦!
集落42軒から一人出席&子供会でちょっとだけにぎやかにスタート
子供会は集落の中を回りましたが、結構きれいで小さなゴミしかありませんでした。でも青木建材さんから集落に入るまでの田んぼ道には空き缶が多く、きっと投げ捨てたんだろうな~とみんな思いました。
1時間半ほどがんばったので、子供たちに「ごほうび!飲み物あるよ~ 」と集落の役員さんが出してくれたのが、なんと「お茶(ペットボトル)とおしるこ(缶)」。
」と集落の役員さんが出してくれたのが、なんと「お茶(ペットボトル)とおしるこ(缶)」。
ええっつおしるこ?と思いながら、子供たちお先にどうぞ~といって渡したら、みんなお茶をチョイス

「子供はおしるこだろ~?」と役員さん。
「いや いまどきの子はおしるこは無いでしょう・・・」と心の中で突っ込んでいたら、「じゃあ親が責任もっておしるこ!」と言われた
いまどきの子はおしるこは無いでしょう・・・」と心の中で突っ込んでいたら、「じゃあ親が責任もっておしるこ!」と言われた
「ええええええ 」と思いながら頂いたものの、まったく飲む気がしないので、義母さんに「おみやげです~
」と思いながら頂いたものの、まったく飲む気がしないので、義母さんに「おみやげです~ 」と渡したら、意外に喜んでくれたので良かったです。
」と渡したら、意外に喜んでくれたので良かったです。
暖かい飲み物には紅茶とかもあるんですよ~ 。今回の飲み物を選んだ方がどうも超甘党だったらしい
。今回の飲み物を選んだ方がどうも超甘党だったらしい
そして午後は、子供会が集落の消防団の皆さんと一緒に「火事注意の声掛け」に参加。
以前より消防団活動で独自に1軒1軒声掛けしていたところに、子供会も地域活動の一環として参加させていただきました。
1軒1軒をまわって声掛けした後に、「火の用心」と拍子木を鳴らしていうのですが、なかなかいい感じ。
先月は恥ずかしくて声も小さかったりタイミングがあわなかったりしたのですが、2回目ともなると慣れてきて上手にできた感じがします。
まわるにあたり、「火の用~心」ケンケン☆と拍子木たたいた方がいいと思って拍子木を買おうと思ったら、どこにも売っていな~い
なので社長(義父)に話したら、昔うちの左官店でお世話になった材木屋さんに行ってみろと言うので行ってみたら、ちょうどきっちり乾燥した野球のバットに使う木があるとのことで、それで拍子木作って頂きました。
木をたたいて鳴らすと、ホームランの時のようなキーンと高い音が出てすごい響きます
もう入手困難なので、大事使わないと~
まずは初回の男子チーム

本日2回目は雨が降ってしまったし、7人中2名欠席でますます人数少ないので、皆でメイン通りをまわりました。

最近集落では、夏祭りも無くなり、いろんな世代が顔を合わせることも無くなってきているので、ラジオ体操をみんなでしようと声かけたり、集落センターにお泊り会したり、今回のように消防活動に一緒に参加させていただき、少しでも子供たちの顔を覚えてもらえればなあと。
顔を覚えてもらえば、登下校や遊んでいるときや何かあったときに挨拶しやすいし、声もかけやすいし、「集落の子
 」として見守って頂けるしの~。
」として見守って頂けるしの~。
田舎でも、昔と違って結構人間関係や世代交流もけっこう希薄になってきてるんですよね・・・ といっても都会よりはまだまだ濃いですがww
といっても都会よりはまだまだ濃いですがww
これがないから・あれがなくなったからと他力の所為にせず、ちょっと視点を変えて攻めの子供会でいこうと思ってます。
まずは、大事な地元からつながっていかないと ですね
ですね

まずは朝7時集合で、地域の皆さんと子供会でクリーン作戦!
集落42軒から一人出席&子供会でちょっとだけにぎやかにスタート

子供会は集落の中を回りましたが、結構きれいで小さなゴミしかありませんでした。でも青木建材さんから集落に入るまでの田んぼ道には空き缶が多く、きっと投げ捨てたんだろうな~とみんな思いました。
1時間半ほどがんばったので、子供たちに「ごほうび!飲み物あるよ~
 」と集落の役員さんが出してくれたのが、なんと「お茶(ペットボトル)とおしるこ(缶)」。
」と集落の役員さんが出してくれたのが、なんと「お茶(ペットボトル)とおしるこ(缶)」。ええっつおしるこ?と思いながら、子供たちお先にどうぞ~といって渡したら、みんなお茶をチョイス


「子供はおしるこだろ~?」と役員さん。
「いや
 いまどきの子はおしるこは無いでしょう・・・」と心の中で突っ込んでいたら、「じゃあ親が責任もっておしるこ!」と言われた
いまどきの子はおしるこは無いでしょう・・・」と心の中で突っ込んでいたら、「じゃあ親が責任もっておしるこ!」と言われた
「ええええええ
 」と思いながら頂いたものの、まったく飲む気がしないので、義母さんに「おみやげです~
」と思いながら頂いたものの、まったく飲む気がしないので、義母さんに「おみやげです~ 」と渡したら、意外に喜んでくれたので良かったです。
」と渡したら、意外に喜んでくれたので良かったです。暖かい飲み物には紅茶とかもあるんですよ~
 。今回の飲み物を選んだ方がどうも超甘党だったらしい
。今回の飲み物を選んだ方がどうも超甘党だったらしい
そして午後は、子供会が集落の消防団の皆さんと一緒に「火事注意の声掛け」に参加。
以前より消防団活動で独自に1軒1軒声掛けしていたところに、子供会も地域活動の一環として参加させていただきました。
1軒1軒をまわって声掛けした後に、「火の用心」と拍子木を鳴らしていうのですが、なかなかいい感じ。
先月は恥ずかしくて声も小さかったりタイミングがあわなかったりしたのですが、2回目ともなると慣れてきて上手にできた感じがします。
まわるにあたり、「火の用~心」ケンケン☆と拍子木たたいた方がいいと思って拍子木を買おうと思ったら、どこにも売っていな~い

なので社長(義父)に話したら、昔うちの左官店でお世話になった材木屋さんに行ってみろと言うので行ってみたら、ちょうどきっちり乾燥した野球のバットに使う木があるとのことで、それで拍子木作って頂きました。
木をたたいて鳴らすと、ホームランの時のようなキーンと高い音が出てすごい響きます

もう入手困難なので、大事使わないと~
まずは初回の男子チーム

本日2回目は雨が降ってしまったし、7人中2名欠席でますます人数少ないので、皆でメイン通りをまわりました。

最近集落では、夏祭りも無くなり、いろんな世代が顔を合わせることも無くなってきているので、ラジオ体操をみんなでしようと声かけたり、集落センターにお泊り会したり、今回のように消防活動に一緒に参加させていただき、少しでも子供たちの顔を覚えてもらえればなあと。
顔を覚えてもらえば、登下校や遊んでいるときや何かあったときに挨拶しやすいし、声もかけやすいし、「集落の子

 」として見守って頂けるしの~。
」として見守って頂けるしの~。田舎でも、昔と違って結構人間関係や世代交流もけっこう希薄になってきてるんですよね・・・
 といっても都会よりはまだまだ濃いですがww
といっても都会よりはまだまだ濃いですがwwこれがないから・あれがなくなったからと他力の所為にせず、ちょっと視点を変えて攻めの子供会でいこうと思ってます。
まずは、大事な地元からつながっていかないと
 ですね
ですね
2012年10月25日
文化伝統と技術を伝える意義
お仕事アップ!というか、写真整理をしていたら、面白い写真が出てきたので書いてみました。
最近民家を建設する際の左官業といえば、基礎工事・玄関ポーチのタイルやコンクリート・ブロック塀・お風呂のタイル貼り(最近めっきり少ないですけど )などがありますが、一番の腕の魅せどころは「壁塗り」なんです。
)などがありますが、一番の腕の魅せどころは「壁塗り」なんです。
左官屋と言いながら、壁塗り出来ない職人さんもおりますので、「壁塗り」は本当に技術がいるものなのです
しかし、白壁の家なんて最近ほとんどなく、なかなか技術を継承する場が無いのが問題です。
そして究極の壁塗りは「土壁」です。
また、壁を塗ることは出来ても、土壁をイチから作れる方が段々減ってきて、この鶴岡市内では3人ほどしかおらず、現役の左官職人ではわが社の社長(義父)だけなのだそうです。
現在庄内には土壁に適した粘土状の土がないので、新潟に仕入れに行きます。
土をこねる際も、硬さやわらの配合など、口で言ってもわからない感覚的なものがあるので、やり方を見て覚えるしか無いのです。
壁の下地には「木舞(こまい)」というものを使いますが、この木舞のを作るときの結び方や幅などは全国の地域によって違い、庄内もまた違うのでした。その風土気候に合わせた独自の方法があるのです。
この写真は、ずいぶん前になりますが、羽黒で土壁の建物を建てるときに、唯一の職人として先生になって欲しいと依頼を受けて、一般の人に木舞の作り方を指導している時のものです。ちなみに、木舞を作るのを「こめかき」といいます。庄内弁だと「こめがぎ」と濁点で言いますww

珍しいので、テレビ局からも取材を受けました
そして社長のほかにも助っ人で、第一線を退いた師匠も来ていただき、うちの職人さんにも指導して頂きました。

土だけだと長持ちしないので、ちょっと現代の素材を入れて長寿命化したりと、きちんと技術を継承しているからこそ出来るアレンジもあるのでした 。
。
なかなかこのような機会がないので、従業員のみんなも大変勉強になりましが、この時私はまだお手伝いもしていなかったので、貴重なデーターを撮る事ができませんでした
技術を知っていても継承できる機会が全くないので、歴史と文化を引き継ぐ為にも、このようなお仕事があればなあ・・・ と最近しみじみ思います。
と最近しみじみ思います。
どんなに良いものでも、必要性がなければ消滅してしまうのか・・・
社長が生きているうちに、もう一度このような機会があったら、今度はイチから十まで撮影&レポートにし、後世に伝承できるようにしていきたいと思ってます。
鶴岡市に鶴ケ岡城でも復活したら、大活躍できるんだろうな・・・ww
最近民家を建設する際の左官業といえば、基礎工事・玄関ポーチのタイルやコンクリート・ブロック塀・お風呂のタイル貼り(最近めっきり少ないですけど
 )などがありますが、一番の腕の魅せどころは「壁塗り」なんです。
)などがありますが、一番の腕の魅せどころは「壁塗り」なんです。左官屋と言いながら、壁塗り出来ない職人さんもおりますので、「壁塗り」は本当に技術がいるものなのです

しかし、白壁の家なんて最近ほとんどなく、なかなか技術を継承する場が無いのが問題です。
そして究極の壁塗りは「土壁」です。
また、壁を塗ることは出来ても、土壁をイチから作れる方が段々減ってきて、この鶴岡市内では3人ほどしかおらず、現役の左官職人ではわが社の社長(義父)だけなのだそうです。
現在庄内には土壁に適した粘土状の土がないので、新潟に仕入れに行きます。
土をこねる際も、硬さやわらの配合など、口で言ってもわからない感覚的なものがあるので、やり方を見て覚えるしか無いのです。
壁の下地には「木舞(こまい)」というものを使いますが、この木舞のを作るときの結び方や幅などは全国の地域によって違い、庄内もまた違うのでした。その風土気候に合わせた独自の方法があるのです。
この写真は、ずいぶん前になりますが、羽黒で土壁の建物を建てるときに、唯一の職人として先生になって欲しいと依頼を受けて、一般の人に木舞の作り方を指導している時のものです。ちなみに、木舞を作るのを「こめかき」といいます。庄内弁だと「こめがぎ」と濁点で言いますww


珍しいので、テレビ局からも取材を受けました

そして社長のほかにも助っ人で、第一線を退いた師匠も来ていただき、うちの職人さんにも指導して頂きました。

土だけだと長持ちしないので、ちょっと現代の素材を入れて長寿命化したりと、きちんと技術を継承しているからこそ出来るアレンジもあるのでした
 。
。なかなかこのような機会がないので、従業員のみんなも大変勉強になりましが、この時私はまだお手伝いもしていなかったので、貴重なデーターを撮る事ができませんでした

技術を知っていても継承できる機会が全くないので、歴史と文化を引き継ぐ為にも、このようなお仕事があればなあ・・・
 と最近しみじみ思います。
と最近しみじみ思います。どんなに良いものでも、必要性がなければ消滅してしまうのか・・・
社長が生きているうちに、もう一度このような機会があったら、今度はイチから十まで撮影&レポートにし、後世に伝承できるようにしていきたいと思ってます。
鶴岡市に鶴ケ岡城でも復活したら、大活躍できるんだろうな・・・ww

2012年10月17日
鶴岡食文化女性リポーター 山ぶどう編レポ その3
その3 最終章
12時40分よりつづいた山ぶどうの体験もついに佳境にはいりました!いよいよ味覚体験の時間です 。
。
「山ブドウを味わう」と題し、一体どんな料理になっているのか楽しみです 。その中でも一番気になっていたのが「ぶどう葉餅」
。その中でも一番気になっていたのが「ぶどう葉餅」 です。「つるおかおうち御膳」という鶴岡の郷土料理をまとめた本の中に、「ブドウと名がついているのにブドウの実じゃなくて葉を使った餅」というおもしろい料理だったので、すごく気になっていたのです。
です。「つるおかおうち御膳」という鶴岡の郷土料理をまとめた本の中に、「ブドウと名がついているのにブドウの実じゃなくて葉を使った餅」というおもしろい料理だったので、すごく気になっていたのです。
私が所属している食生活改善推進協議会羽黒の役員メンバーも、食べたことある人がいないので、今回もしかしたら出るかな?とすごくワクワク
そして田麦荘さんは国道112号を通るたび、横目でちらっと見ていましたが、中に入るのも初めてだったので、これもまたワクワク
懐かしい雰囲気のロビーに入り、着替えをして、大広間に移動。ずらっとお膳が並び圧巻です。

席に座ったらありました!ぶどう葉餅です!やっほう

乾杯の後に次から次へとお料理がやってきますが、どれも山ブドウが使われていて、しかも山ぶどうの味が上手に引き出され、他の材料の味とみごとにマッチしていて、予想外のコラボレーション

この日のために、なんば農園の難波さんと料理長の渋谷さんが2週間かけて考えてくれたお料理なのだそうです。今回限りのスペシャルメニュー 山ぶどうの味を知り尽くした方だからこそ出来たメニューなのですね!
山ぶどうの味を知り尽くした方だからこそ出来たメニューなのですね!
中でも私が珍しいと思ったのが4つ。
①アケビの山ブドウ漬け(山ブドウの味とほのかなアケビの苦みがベストマッチ!)
(写真右上参照)

②山ブドウのを使った牛たたき寿司(ごはんに山ぶどうの味がこんなにあうなんて~!寿し酢よりもなんだか上品!)
(写真左下参照)

③なんど大根のすり流し なめこ・針柚子入り (なんだか梨のすりおろしのようにまったりととろみがあるのはナゼ?ほのかに甘くて不思議な触感)(写真中央上参照)
なんど大根ってなんだ?と思っていたら、田麦地区の「なんど山」というところに植えた大根だからとのこと。普通の青くび大根を植えているのだけど、なんど山に植えると味がとても美味しくなり、梨のような独自の触感と甘味になるのだそうです。生で食べても普通の大根と味が全く違うので、違う大根をだしてもすぐわかるのだとおかみさんが説明してくれました。
標高が違うだけで、同じ大根がこんなに味が変わることにびっくりです!山はまさに様々な命の母体なのですね。
④ぶどう葉餅(ブドウの葉を使った餅)
おかみさんの説明によると、6月の新芽と若葉のブドウの葉を収穫し(6月の若葉以外は使わない)、乾燥させたらあく水で柔らかく煮て、もち米に混ぜて蒸しあげ、餅にしてあんこをいれて丸めて作り、朝日ではぶどうっぱ餅というそうです。今回は柔らかさを出すために、ジャガイモを混ぜて餅にしたそうです。乾燥した葉も見せてくれましたが、全くブドウ色じゃないな~

これら以外にも沢山のお料理で山ブドウのよさを満喫!全部食べきっておなか一杯!美味しかった~
ツアーの方たちとも和気あいあいと庄内の料理の話でもりあがり、別れを惜しみつつ味覚体験が終了し、帰るときにぶどう葉餅のお土産を売っていたので、2パック購入してかえりました。パックには「古代もち」と木のタグが入っていたので、「あれ?ブドウ葉餅って書いてない?」と気になり翌日調べてみたら・・・
干したブドウの葉を入れて餅を作る地区は、朝日地域と温海地域の2か所あり、朝日は「ぶどうっぱ(葉)餅」とよび、温海地域は「古代餅」と呼ぶのでした。

緑色は草餅で、黒っぽい色がぶどう葉餅です
温海の作り方は、蒸した米の上にあく水で柔らかく煮た乾燥ブドウ葉をちぎってのせ、さらに蒸すのに対し、朝日は米とあく水で柔らかく煮たブドウ葉を初めから一緒に蒸しあげるところが違うだけで、他の工程はほとんど一緒なのでした。
味は・・・すばり美味しい!んめ~ 売っていたら、是非一度食べてみてください。おすすめです!
売っていたら、是非一度食べてみてください。おすすめです!
呼び方は違えど、中身は同じ!摩耶山を隔ててほぼ同じ地域食が伝わっているところが、文化の交流が昔からあったのだなあと、なんだかうれしくなりました。
今回の「鶴岡食文化女性リポーター山ぶどう編」大変楽しく、また新たな発見が多く、この鶴岡の食の豊かさを改めて実感しました。多くの方々の努力により受け継がれてきた伝統とこの自然豊かな鶴岡を、もっと沢山の方に知って足を運んで頂きたいと思いました。
そして子供たちにも「鶴岡ってすげーんだぜ 」と胸をはってもらえるよう、いろんな食文化を伝えて行きたいと思います。
」と胸をはってもらえるよう、いろんな食文化を伝えて行きたいと思います。
12時40分よりつづいた山ぶどうの体験もついに佳境にはいりました!いよいよ味覚体験の時間です
 。
。「山ブドウを味わう」と題し、一体どんな料理になっているのか楽しみです
 。その中でも一番気になっていたのが「ぶどう葉餅」
。その中でも一番気になっていたのが「ぶどう葉餅」 です。「つるおかおうち御膳」という鶴岡の郷土料理をまとめた本の中に、「ブドウと名がついているのにブドウの実じゃなくて葉を使った餅」というおもしろい料理だったので、すごく気になっていたのです。
です。「つるおかおうち御膳」という鶴岡の郷土料理をまとめた本の中に、「ブドウと名がついているのにブドウの実じゃなくて葉を使った餅」というおもしろい料理だったので、すごく気になっていたのです。私が所属している食生活改善推進協議会羽黒の役員メンバーも、食べたことある人がいないので、今回もしかしたら出るかな?とすごくワクワク

そして田麦荘さんは国道112号を通るたび、横目でちらっと見ていましたが、中に入るのも初めてだったので、これもまたワクワク

懐かしい雰囲気のロビーに入り、着替えをして、大広間に移動。ずらっとお膳が並び圧巻です。

席に座ったらありました!ぶどう葉餅です!やっほう


乾杯の後に次から次へとお料理がやってきますが、どれも山ブドウが使われていて、しかも山ぶどうの味が上手に引き出され、他の材料の味とみごとにマッチしていて、予想外のコラボレーション


この日のために、なんば農園の難波さんと料理長の渋谷さんが2週間かけて考えてくれたお料理なのだそうです。今回限りのスペシャルメニュー
 山ぶどうの味を知り尽くした方だからこそ出来たメニューなのですね!
山ぶどうの味を知り尽くした方だからこそ出来たメニューなのですね!
中でも私が珍しいと思ったのが4つ。
①アケビの山ブドウ漬け(山ブドウの味とほのかなアケビの苦みがベストマッチ!)
(写真右上参照)

②山ブドウのを使った牛たたき寿司(ごはんに山ぶどうの味がこんなにあうなんて~!寿し酢よりもなんだか上品!)
(写真左下参照)

③なんど大根のすり流し なめこ・針柚子入り (なんだか梨のすりおろしのようにまったりととろみがあるのはナゼ?ほのかに甘くて不思議な触感)(写真中央上参照)
なんど大根ってなんだ?と思っていたら、田麦地区の「なんど山」というところに植えた大根だからとのこと。普通の青くび大根を植えているのだけど、なんど山に植えると味がとても美味しくなり、梨のような独自の触感と甘味になるのだそうです。生で食べても普通の大根と味が全く違うので、違う大根をだしてもすぐわかるのだとおかみさんが説明してくれました。
標高が違うだけで、同じ大根がこんなに味が変わることにびっくりです!山はまさに様々な命の母体なのですね。
④ぶどう葉餅(ブドウの葉を使った餅)
おかみさんの説明によると、6月の新芽と若葉のブドウの葉を収穫し(6月の若葉以外は使わない)、乾燥させたらあく水で柔らかく煮て、もち米に混ぜて蒸しあげ、餅にしてあんこをいれて丸めて作り、朝日ではぶどうっぱ餅というそうです。今回は柔らかさを出すために、ジャガイモを混ぜて餅にしたそうです。乾燥した葉も見せてくれましたが、全くブドウ色じゃないな~

これら以外にも沢山のお料理で山ブドウのよさを満喫!全部食べきっておなか一杯!美味しかった~

ツアーの方たちとも和気あいあいと庄内の料理の話でもりあがり、別れを惜しみつつ味覚体験が終了し、帰るときにぶどう葉餅のお土産を売っていたので、2パック購入してかえりました。パックには「古代もち」と木のタグが入っていたので、「あれ?ブドウ葉餅って書いてない?」と気になり翌日調べてみたら・・・
干したブドウの葉を入れて餅を作る地区は、朝日地域と温海地域の2か所あり、朝日は「ぶどうっぱ(葉)餅」とよび、温海地域は「古代餅」と呼ぶのでした。

緑色は草餅で、黒っぽい色がぶどう葉餅です
温海の作り方は、蒸した米の上にあく水で柔らかく煮た乾燥ブドウ葉をちぎってのせ、さらに蒸すのに対し、朝日は米とあく水で柔らかく煮たブドウ葉を初めから一緒に蒸しあげるところが違うだけで、他の工程はほとんど一緒なのでした。
味は・・・すばり美味しい!んめ~
 売っていたら、是非一度食べてみてください。おすすめです!
売っていたら、是非一度食べてみてください。おすすめです!呼び方は違えど、中身は同じ!摩耶山を隔ててほぼ同じ地域食が伝わっているところが、文化の交流が昔からあったのだなあと、なんだかうれしくなりました。
今回の「鶴岡食文化女性リポーター山ぶどう編」大変楽しく、また新たな発見が多く、この鶴岡の食の豊かさを改めて実感しました。多くの方々の努力により受け継がれてきた伝統とこの自然豊かな鶴岡を、もっと沢山の方に知って足を運んで頂きたいと思いました。
そして子供たちにも「鶴岡ってすげーんだぜ
 」と胸をはってもらえるよう、いろんな食文化を伝えて行きたいと思います。
」と胸をはってもらえるよう、いろんな食文化を伝えて行きたいと思います。2012年10月15日
鶴岡食文化女性リポーター 山ぶどう編レポ その2
つづき その2
お話を聞いていた公民館から畑が近いので、歩いて早速見学。途中にクルミが落ちていたりして探検気分♪
畑はぐるっと網で囲ってあり、中に入ると、ブドウは縦に棚が並んで栽培してありました。1・5町歩(ちょうぶ)も作付しているうちのほんの一角なのに、整然と並んですごいです!

まるでワイナリーのブドウ畑のよう。葉は一枚一枚が大きく、山ぶどうがすっかり隠れてしまって、葉をめくりながら探す感じです。

難波さんよりブドウの取り方を指導いただき、早速収穫体験開始!「一袋で大体1キロ位になるから、それくらい採ってもいいよ」とのこと。

(しかし、難波さんって小泉純一郎さんに似てるな~ )
)
「奥の棚は猿が食べたけど、結構粒大きいよ」と仰るので、奥にぞろぞろ移動。
雨が降っているときは収穫しないのですが、今回はジャム用なので(ジャムにするときは水洗いするから)大丈夫なんだそうです。ジュースにするときは、表面の白い酵母が必要なので洗わないそうです。
葉の状態もきれいだったし、山なので「どんな虫がくるのですか?」と質問したら、「いろんな虫がくる 」そうです。「コガネムシとか?」と聞いたら「それも来るけど、ホントにいろんな虫が来る」とのことで、薄く消毒を何度か散布するそうです。収穫の1か月前からは消毒をやめて、自然にまかせた状態にするそうです。
」そうです。「コガネムシとか?」と聞いたら「それも来るけど、ホントにいろんな虫が来る」とのことで、薄く消毒を何度か散布するそうです。収穫の1か月前からは消毒をやめて、自然にまかせた状態にするそうです。
雪の多い場所なので、冬前に棚からツルをはずし、春になるとまた棚にツルを固定するという、大変な労力がかかっています。この量を考えて想像するだけで軽くめまいが・・・
葉をめくると、様々な表情の山ブドウが「しまった!見つかっちまったぜ 」と顔をだします。黒くて粒が大きめなのが甘いので、探しながら収穫
」と顔をだします。黒くて粒が大きめなのが甘いので、探しながら収穫 。
。

皆たくさん収穫し、ニコニコで記念撮影
生まれて初めて山ぶどうを、収穫させていただきました。山をかき分け木に登って取らなくてもいいって素晴らしい~
でもこの体験、一般の方でも事前に申し込みがあれば、収穫体験できるそうですよ!
山ブドウを見てはにんまりしつつ 、夕食会場の田麦荘にバスで移動するのでした。
、夕食会場の田麦荘にバスで移動するのでした。
その3につづく
お話を聞いていた公民館から畑が近いので、歩いて早速見学。途中にクルミが落ちていたりして探検気分♪
畑はぐるっと網で囲ってあり、中に入ると、ブドウは縦に棚が並んで栽培してありました。1・5町歩(ちょうぶ)も作付しているうちのほんの一角なのに、整然と並んですごいです!

まるでワイナリーのブドウ畑のよう。葉は一枚一枚が大きく、山ぶどうがすっかり隠れてしまって、葉をめくりながら探す感じです。

難波さんよりブドウの取り方を指導いただき、早速収穫体験開始!「一袋で大体1キロ位になるから、それくらい採ってもいいよ」とのこと。

(しかし、難波さんって小泉純一郎さんに似てるな~
 )
)「奥の棚は猿が食べたけど、結構粒大きいよ」と仰るので、奥にぞろぞろ移動。
雨が降っているときは収穫しないのですが、今回はジャム用なので(ジャムにするときは水洗いするから)大丈夫なんだそうです。ジュースにするときは、表面の白い酵母が必要なので洗わないそうです。
葉の状態もきれいだったし、山なので「どんな虫がくるのですか?」と質問したら、「いろんな虫がくる
 」そうです。「コガネムシとか?」と聞いたら「それも来るけど、ホントにいろんな虫が来る」とのことで、薄く消毒を何度か散布するそうです。収穫の1か月前からは消毒をやめて、自然にまかせた状態にするそうです。
」そうです。「コガネムシとか?」と聞いたら「それも来るけど、ホントにいろんな虫が来る」とのことで、薄く消毒を何度か散布するそうです。収穫の1か月前からは消毒をやめて、自然にまかせた状態にするそうです。雪の多い場所なので、冬前に棚からツルをはずし、春になるとまた棚にツルを固定するという、大変な労力がかかっています。この量を考えて想像するだけで軽くめまいが・・・

葉をめくると、様々な表情の山ブドウが「しまった!見つかっちまったぜ
 」と顔をだします。黒くて粒が大きめなのが甘いので、探しながら収穫
」と顔をだします。黒くて粒が大きめなのが甘いので、探しながら収穫 。
。
皆たくさん収穫し、ニコニコで記念撮影
生まれて初めて山ぶどうを、収穫させていただきました。山をかき分け木に登って取らなくてもいいって素晴らしい~

でもこの体験、一般の方でも事前に申し込みがあれば、収穫体験できるそうですよ!
山ブドウを見てはにんまりしつつ
 、夕食会場の田麦荘にバスで移動するのでした。
、夕食会場の田麦荘にバスで移動するのでした。その3につづく
2012年10月15日
鶴岡食文化女性リポーター 山ぶどう編レポ その1
最近お仕事をアップしていませんが、多くの方に知ってほしいので、このたびの鶴岡食文化女性リポーター活動のレポートを上げさせていただきます~
我が家には、栗・アケビ・すもも・くるみ・ぶどう等など個人の家にしては実のなる木を多く栽培しており(一応左官屋ですよ~ )、この度の「鶴岡女性リポーター第4弾山編」では、野生のブドウを栽培している方からお話が聞けるので、すごく楽しみにしておりました。
)、この度の「鶴岡女性リポーター第4弾山編」では、野生のブドウを栽培している方からお話が聞けるので、すごく楽しみにしておりました。
天気が悪かったので、完全防備の為に、我が家で交通誘導で使用するカッパ上下着込んで臨みました
今回の講師は、なんば農園(山ぶどう農家)の難波裕一さんです。お爺ちゃんの代から山ブドウを栽培。日本で初めて鶴岡で山ぶどうの栽培を確立したそうです!

昔、朝日にはこれといった作物がなく、山葡萄を特産にしてはどうだろう?と試行錯誤の連続で栽培を始めたそうです。
挿し木にしても生えたけど3~5年たっても実がならず、山形大学と共同研究し、数年かかってブドウの木には雄雌があるのを発見!それでも実がならず、さらに受粉が必要だった!とわかって、受粉したところようやく結実に成功し、今日に至ったそうです 。
。
このお話を聞いたとき、イチョウやあけびも結実するには雌雄の木が必要なので、山ぶどうもまた太古からある木の一つなのだな~と思いました。子孫を残すのに雌雄どちらが欠けてもいけないなんて、木だけどなんだか素敵ですね
そして野生種からの栽培なので、個体によって味が異なるそうです。今は雌木10本に1本の雄木の割合で植えているけど、雄の木の花を農協に持っていき、花粉を取り出してもらい、受粉は機械で行うとのこと。
すぐりもぎはせず、ツルの剪定は夏に行う。10月は鳥や猿の被害があり、猿は団体でやってくるので追い払うのが大変なのだそうです。
今見ている山ブドウが長年の努力のもとで、こうして私たちの手に届いてるとわかり感動 。
。
現在栽培者は100名ほどで、ぶどう部会として活動しているとのこと。
皆がみな栽培方法が違うので、それぞれが先生なんだそうです(それもまたすごい !)
!)
他県でも山ぶどうを栽培しているそうですが、なり方・収穫量からしても朝日が№1と自負。現在、朝日1号・月山1~5号まであり、1~2号は9月いっぱい、3~5号は11月まで収穫できるそうです。「見分け方は?」と質問したら、「一番早くなったのが1号ww」とのこと。アバウト~
朝日地域でも山ぶどうの原液は、お客さんがきても飲ませない。自分の薬としておちょこで少しずつ飲んだそうです。
昔から鶴岡の地元でも滋養の薬として広く飲まれており、私も妊婦の時は「貧血予防と血行よくなるから飲みなさい~」と義母に進められて飲んでました。しかし、その時にのんでいた山ぶどうの原液は、顔が最強しかめっ面 になるほど酸っぱいものだったので、今回の山ぶどう原液も同じなのかとドキドキしながらのんだら「あれっ?山ぶどう?」と思うほど美味しい。
になるほど酸っぱいものだったので、今回の山ぶどう原液も同じなのかとドキドキしながらのんだら「あれっ?山ぶどう?」と思うほど美味しい。
隣にいたツアーの方も「なんだか酸っぱくて美味しいわ~運動してないのに、体がぽかぽかするわ~ 」と不思議がってます。早速血行が良くなったのですね!効果早いな~
」と不思議がってます。早速血行が良くなったのですね!効果早いな~
「この山ぶどうは酸っぱくない 」というと、「それは品種の違いですよ
」というと、「それは品種の違いですよ 」と難波さん。
」と難波さん。
ううううっ あの時こういう山ブドウ原液飲みたかったです・・・
あの時こういう山ブドウ原液飲みたかったです・・・
お話の合間に、山からとってきました~というキノコ汁がふるまわれ、
 見たこともないキノコがたくさん入ってましたが、すっごい美味し~。
見たこともないキノコがたくさん入ってましたが、すっごい美味し~。
ちなみに赤いきのこは「ますたけ」だそうです。
食べ終わると、早速準備して頂いた山ぶどうでジュース作り。山ブドウワインは糖度18度以上のものを使うのですが、今回準備していただいたのは、17~18度のブドウ。
手で房から粒を取りますが、野生種なゆえかしっかりついているので、ぶちっと引っ張って取らないとなかなか取れない。ホントに山に生えてるブドウは、もっと粒がバラバラで小さい感じなのですが、作付した山ぶどうは粒も大きく、沢山ついています。

房をなんとかはずし、つぶす段階で「踏んでもいいですよ」と言われたので、ふみふみ。
なんとも言えない ぷちぶち感覚wおもしろーい

ウキウキ踏んでいたら、「踏みすぎてビニール切らさないように気を付けてくださいね~ 」と言われ、途中から慎重にフミフミ。
」と言われ、途中から慎重にフミフミ。
つぶした山ぶどうは1週間おいてからザルでこして皮と液体に分け、液体はペットボトルに入れて保管。皮は再度水と砂糖を入れて煮だすと、2番ジュースができるそうです。漬物の色付けにも使ったり、さまざま最後まで使い切るそうです。種が4つも入ってるので、干しブドウとか加工食品には向かないとのこと。
そして山ぶどう原液で作ったジャムとその」山ぶどう原液を飲ませて頂きました!


ジャムすっごいおいしい~そのまま全部食べられる~と一同笑顔。ブドウ色なのに、普通のブドウとは違うしっかりした味!
原液はボトルごと味が少しずつ違う。3杯も飲むと冷え性な私も体がぽかぽかしてきて、さすが昔からお薬と重宝されているのがわかります。「ちょっと山に登ってきます!」と思わず言ってしまいそうな勢いです
原液だと長期保存可能で、1年くらいになるとワイン状態になるそうです 。
。
鶴岡に住んでいながら、知らないことが沢山あるな~とまたこのリポーター活動で学びました。鶴岡の食文化は深いデス
山ぶどうがこんなにおいしく気軽に頂けるのは、やはり長年苦労を重ねて栽培してきてくれた難波さんたちのおかげだなあと思いつつ、今度はその山ぶどうの畑に連れていってくださるそうです。
どんな風な畑?なのか楽しみ~♪
その2へ続く

我が家には、栗・アケビ・すもも・くるみ・ぶどう等など個人の家にしては実のなる木を多く栽培しており(一応左官屋ですよ~
 )、この度の「鶴岡女性リポーター第4弾山編」では、野生のブドウを栽培している方からお話が聞けるので、すごく楽しみにしておりました。
)、この度の「鶴岡女性リポーター第4弾山編」では、野生のブドウを栽培している方からお話が聞けるので、すごく楽しみにしておりました。天気が悪かったので、完全防備の為に、我が家で交通誘導で使用するカッパ上下着込んで臨みました

今回の講師は、なんば農園(山ぶどう農家)の難波裕一さんです。お爺ちゃんの代から山ブドウを栽培。日本で初めて鶴岡で山ぶどうの栽培を確立したそうです!

昔、朝日にはこれといった作物がなく、山葡萄を特産にしてはどうだろう?と試行錯誤の連続で栽培を始めたそうです。
挿し木にしても生えたけど3~5年たっても実がならず、山形大学と共同研究し、数年かかってブドウの木には雄雌があるのを発見!それでも実がならず、さらに受粉が必要だった!とわかって、受粉したところようやく結実に成功し、今日に至ったそうです
 。
。このお話を聞いたとき、イチョウやあけびも結実するには雌雄の木が必要なので、山ぶどうもまた太古からある木の一つなのだな~と思いました。子孫を残すのに雌雄どちらが欠けてもいけないなんて、木だけどなんだか素敵ですね

そして野生種からの栽培なので、個体によって味が異なるそうです。今は雌木10本に1本の雄木の割合で植えているけど、雄の木の花を農協に持っていき、花粉を取り出してもらい、受粉は機械で行うとのこと。
すぐりもぎはせず、ツルの剪定は夏に行う。10月は鳥や猿の被害があり、猿は団体でやってくるので追い払うのが大変なのだそうです。
今見ている山ブドウが長年の努力のもとで、こうして私たちの手に届いてるとわかり感動
 。
。現在栽培者は100名ほどで、ぶどう部会として活動しているとのこと。
皆がみな栽培方法が違うので、それぞれが先生なんだそうです(それもまたすごい
 !)
!)他県でも山ぶどうを栽培しているそうですが、なり方・収穫量からしても朝日が№1と自負。現在、朝日1号・月山1~5号まであり、1~2号は9月いっぱい、3~5号は11月まで収穫できるそうです。「見分け方は?」と質問したら、「一番早くなったのが1号ww」とのこと。アバウト~

朝日地域でも山ぶどうの原液は、お客さんがきても飲ませない。自分の薬としておちょこで少しずつ飲んだそうです。
昔から鶴岡の地元でも滋養の薬として広く飲まれており、私も妊婦の時は「貧血予防と血行よくなるから飲みなさい~」と義母に進められて飲んでました。しかし、その時にのんでいた山ぶどうの原液は、顔が最強しかめっ面
 になるほど酸っぱいものだったので、今回の山ぶどう原液も同じなのかとドキドキしながらのんだら「あれっ?山ぶどう?」と思うほど美味しい。
になるほど酸っぱいものだったので、今回の山ぶどう原液も同じなのかとドキドキしながらのんだら「あれっ?山ぶどう?」と思うほど美味しい。隣にいたツアーの方も「なんだか酸っぱくて美味しいわ~運動してないのに、体がぽかぽかするわ~
 」と不思議がってます。早速血行が良くなったのですね!効果早いな~
」と不思議がってます。早速血行が良くなったのですね!効果早いな~
「この山ぶどうは酸っぱくない
 」というと、「それは品種の違いですよ
」というと、「それは品種の違いですよ 」と難波さん。
」と難波さん。ううううっ
 あの時こういう山ブドウ原液飲みたかったです・・・
あの時こういう山ブドウ原液飲みたかったです・・・お話の合間に、山からとってきました~というキノコ汁がふるまわれ、

 見たこともないキノコがたくさん入ってましたが、すっごい美味し~。
見たこともないキノコがたくさん入ってましたが、すっごい美味し~。ちなみに赤いきのこは「ますたけ」だそうです。
食べ終わると、早速準備して頂いた山ぶどうでジュース作り。山ブドウワインは糖度18度以上のものを使うのですが、今回準備していただいたのは、17~18度のブドウ。
手で房から粒を取りますが、野生種なゆえかしっかりついているので、ぶちっと引っ張って取らないとなかなか取れない。ホントに山に生えてるブドウは、もっと粒がバラバラで小さい感じなのですが、作付した山ぶどうは粒も大きく、沢山ついています。

房をなんとかはずし、つぶす段階で「踏んでもいいですよ」と言われたので、ふみふみ。
なんとも言えない ぷちぶち感覚wおもしろーい

ウキウキ踏んでいたら、「踏みすぎてビニール切らさないように気を付けてくださいね~
 」と言われ、途中から慎重にフミフミ。
」と言われ、途中から慎重にフミフミ。つぶした山ぶどうは1週間おいてからザルでこして皮と液体に分け、液体はペットボトルに入れて保管。皮は再度水と砂糖を入れて煮だすと、2番ジュースができるそうです。漬物の色付けにも使ったり、さまざま最後まで使い切るそうです。種が4つも入ってるので、干しブドウとか加工食品には向かないとのこと。
そして山ぶどう原液で作ったジャムとその」山ぶどう原液を飲ませて頂きました!


ジャムすっごいおいしい~そのまま全部食べられる~と一同笑顔。ブドウ色なのに、普通のブドウとは違うしっかりした味!
原液はボトルごと味が少しずつ違う。3杯も飲むと冷え性な私も体がぽかぽかしてきて、さすが昔からお薬と重宝されているのがわかります。「ちょっと山に登ってきます!」と思わず言ってしまいそうな勢いです

原液だと長期保存可能で、1年くらいになるとワイン状態になるそうです
 。
。鶴岡に住んでいながら、知らないことが沢山あるな~とまたこのリポーター活動で学びました。鶴岡の食文化は深いデス

山ぶどうがこんなにおいしく気軽に頂けるのは、やはり長年苦労を重ねて栽培してきてくれた難波さんたちのおかげだなあと思いつつ、今度はその山ぶどうの畑に連れていってくださるそうです。
どんな風な畑?なのか楽しみ~♪
その2へ続く
2012年10月13日
山伏さんと一緒に羽黒町研修会 斎館編
時間を30分もオーバーしてしまい、慌てて斎館にバスに乗って移動
地元の運転手さんなので、一般車両通行止めの通路をどこまでも車で行き、一体大丈夫なのか?ってほど近くに停めて降車。
こんなところに駐車場あったなの~と感心しつつ、斎館に歩いていきました。

昼食前に料理長さんのお話を聞くという予定で、11時30分からの予定が12時になってしまいました。このあとに別の約束が入っていた料理長さんでしたが、我々の為に時間をおして待っていてくださいました。
遅くなってすみません
全員そろったところで、待ってましたとばかりに、早速講和にはいります。

昨年ヨーロッパに精進料理を作りに行ってきた、伊藤新吉料理長。
当初6月の予定だったのが、震災の影響で10月に変更になり、山菜が持ち込めなくなってしまったそうな。材料がないと精進料理ができないけど、そんなこと言ってられない状況だったので、知恵をしぼって材料準備を地元で行ったそうです。
幸いフランスだったので、キノコは沢山あるから、それを使ってがんもどきを作ったり、水が硬水なので、ゴマ豆腐がかたまりにくく(硬水で固まらないなんて初めて知ったよ )、コーンスターチで代用したり、浅漬けも現地の野菜で合うものを探したりと、今までの考えが吹っ飛んでしまったが、ここ(庄内)でなければ作れないということはない!と分かったそうです。
)、コーンスターチで代用したり、浅漬けも現地の野菜で合うものを探したりと、今までの考えが吹っ飛んでしまったが、ここ(庄内)でなければ作れないということはない!と分かったそうです。
そして、今まで計量なんてしたことないのに、フランスに行くとき初めて計量したそうです。それまでは、専用のどんぶりで量っていたそうです
「こんなあんばい」を数値化するのは実に大変めんどくさかったそうです。
そして、それを機にNHKなどで料理教室も引き受けたりして、ゴマ豆腐のレシピも公開するようにしたそうです。
何故かというと、教えても感覚というのは伝わらないので、みな同じように出来ない事。そして今まで秘密だった分量を公開して文化がすたれないようにしたほうが、はるかにメリットがあるという事をフランスにいって学んだのだそうです。
この経験をふまえて、新しい精進料理「涼風膳」というのを作ったそうです。
素晴らしい・・・ いくつになっても、経験というのは既成概念を吹き飛ばせるのですね
いくつになっても、経験というのは既成概念を吹き飛ばせるのですね
「ではそのゴマ豆腐の分量教えてください!」とまたもやレディース。でも今回は「よくぞ聞いた !」と心の中で拍手喝采ww
!」と心の中で拍手喝采ww
斎館のゴマ豆腐の分量は・・・
水・・・3L、 すりごま・・・700g、 片栗粉・・・375g、 酒・・・1合 これで42個分だそうです。
火の加減、ねり方・タイミングなどみんな違うので同じには作れないそうです。
そうなんだ~フムフムと感心している間に時間になってしまい、お話は終了。
待ちに待ったお昼ご飯~ 精進料理~
精進料理~


このお料理に至るまで、羽黒山の歴史、大笈酒と勉強してきていただくので、感慨深くお料理をいただきました!
ただ食べるのではなく、そこに至るまでのさまざまなストーリーが美味しさをより一層引き立てます!
山の命をいただく精進料理。これからも大事にしていきたいものです!

地元の運転手さんなので、一般車両通行止めの通路をどこまでも車で行き、一体大丈夫なのか?ってほど近くに停めて降車。
こんなところに駐車場あったなの~と感心しつつ、斎館に歩いていきました。

昼食前に料理長さんのお話を聞くという予定で、11時30分からの予定が12時になってしまいました。このあとに別の約束が入っていた料理長さんでしたが、我々の為に時間をおして待っていてくださいました。
遅くなってすみません

全員そろったところで、待ってましたとばかりに、早速講和にはいります。

昨年ヨーロッパに精進料理を作りに行ってきた、伊藤新吉料理長。
当初6月の予定だったのが、震災の影響で10月に変更になり、山菜が持ち込めなくなってしまったそうな。材料がないと精進料理ができないけど、そんなこと言ってられない状況だったので、知恵をしぼって材料準備を地元で行ったそうです。
幸いフランスだったので、キノコは沢山あるから、それを使ってがんもどきを作ったり、水が硬水なので、ゴマ豆腐がかたまりにくく(硬水で固まらないなんて初めて知ったよ
 )、コーンスターチで代用したり、浅漬けも現地の野菜で合うものを探したりと、今までの考えが吹っ飛んでしまったが、ここ(庄内)でなければ作れないということはない!と分かったそうです。
)、コーンスターチで代用したり、浅漬けも現地の野菜で合うものを探したりと、今までの考えが吹っ飛んでしまったが、ここ(庄内)でなければ作れないということはない!と分かったそうです。そして、今まで計量なんてしたことないのに、フランスに行くとき初めて計量したそうです。それまでは、専用のどんぶりで量っていたそうです

「こんなあんばい」を数値化するのは実に大変めんどくさかったそうです。
そして、それを機にNHKなどで料理教室も引き受けたりして、ゴマ豆腐のレシピも公開するようにしたそうです。
何故かというと、教えても感覚というのは伝わらないので、みな同じように出来ない事。そして今まで秘密だった分量を公開して文化がすたれないようにしたほうが、はるかにメリットがあるという事をフランスにいって学んだのだそうです。
この経験をふまえて、新しい精進料理「涼風膳」というのを作ったそうです。
素晴らしい・・・
 いくつになっても、経験というのは既成概念を吹き飛ばせるのですね
いくつになっても、経験というのは既成概念を吹き飛ばせるのですね
「ではそのゴマ豆腐の分量教えてください!」とまたもやレディース。でも今回は「よくぞ聞いた
 !」と心の中で拍手喝采ww
!」と心の中で拍手喝采ww斎館のゴマ豆腐の分量は・・・
水・・・3L、 すりごま・・・700g、 片栗粉・・・375g、 酒・・・1合 これで42個分だそうです。
火の加減、ねり方・タイミングなどみんな違うので同じには作れないそうです。
そうなんだ~フムフムと感心している間に時間になってしまい、お話は終了。
待ちに待ったお昼ご飯~
 精進料理~
精進料理~

このお料理に至るまで、羽黒山の歴史、大笈酒と勉強してきていただくので、感慨深くお料理をいただきました!
ただ食べるのではなく、そこに至るまでのさまざまなストーリーが美味しさをより一層引き立てます!
山の命をいただく精進料理。これからも大事にしていきたいものです!
2012年10月08日
予想外のガラス拾いに悪戦苦闘
ちょっと真面目にお仕事のお話し。
「8日に仕事してください」と指定されていたのに、うっかり忘れていた社長 。午前中のメールチェックでその連絡メールを発見し、慌てて3人で松山の現場にGO
。午前中のメールチェックでその連絡メールを発見し、慌てて3人で松山の現場にGO !
!
現場を見るなり、あまりのガラスの飛散ぶりにガックリ・・・ 。
。

まさかこんなにガラスが粉々とは思っていなかったので、びっくりしました。
一体何時間かかるんだ?と思ったものの、黙々と拾いました。
薄手のゴム手袋していたのですが、1枚ではゴムを突き抜けてガラスがチクチク手に刺さるので、2枚重ね。

土の割れ目に潜り込んでいたり、稲の根元に紛れ込んでいたり、くいがけの周りにもガラスが飛び散っていたので、稲のなかにあったら大変と、隈なく丁寧に破片探し。
ドライバーで溝からかき出したり、スコップで土を掘り出して選別したりと、お昼も食べずに3時間半かかって、全て手作業で拾い集めました 。
。

これで、来年も土に影響なく稲作が出来るかな?
田んぼの事を考えると手を抜けないので、キッチリ拾ってきました!
また美味しいお米ができますように

「8日に仕事してください」と指定されていたのに、うっかり忘れていた社長
 。午前中のメールチェックでその連絡メールを発見し、慌てて3人で松山の現場にGO
。午前中のメールチェックでその連絡メールを発見し、慌てて3人で松山の現場にGO !
!現場を見るなり、あまりのガラスの飛散ぶりにガックリ・・・
 。
。
まさかこんなにガラスが粉々とは思っていなかったので、びっくりしました。
一体何時間かかるんだ?と思ったものの、黙々と拾いました。
薄手のゴム手袋していたのですが、1枚ではゴムを突き抜けてガラスがチクチク手に刺さるので、2枚重ね。

土の割れ目に潜り込んでいたり、稲の根元に紛れ込んでいたり、くいがけの周りにもガラスが飛び散っていたので、稲のなかにあったら大変と、隈なく丁寧に破片探し。
ドライバーで溝からかき出したり、スコップで土を掘り出して選別したりと、お昼も食べずに3時間半かかって、全て手作業で拾い集めました
 。
。
これで、来年も土に影響なく稲作が出来るかな?
田んぼの事を考えると手を抜けないので、キッチリ拾ってきました!
また美味しいお米ができますように


2012年10月04日
山伏さんと一緒に羽黒町研修会 いでは文化記念館編
階段をフウフウ登り、やってきました「いでは文化記念館」
精進料理をお昼にいただく予定ですが、ただ食べるのでは研修の意味がないので、精進料理の歴史を学ぼうと、
「 日本一の品数といわれる羽黒山に伝わるもっとも豪華な精進料理 幻の精進料理「大笈酒(おおおいさけ)」 」
幻の精進料理「大笈酒(おおおいさけ)」 」
のお勉強をさせていただきました。「お」がやたらと多いので、「お~いさけ」と呼びがちですが(私だけ ?)、「おお おい さけ」なんですよ!
?)、「おお おい さけ」なんですよ!

勉強するにあたり、「学芸員さんから案内してもらいましょう」と成瀬さんから提案をいただいた際、「いではに学芸員さんっているんですか ?」と思わず驚いてしまいました。すみません
?」と思わず驚いてしまいました。すみません いではの存在意義がわかってなーい
いではの存在意義がわかってなーい
どやどやと受付を済ますと、なんだか華奢でかわいらしい方が登場。
「もしや彼女が学芸員さん?! 」とワクワクしていたら、またもや
」とワクワクしていたら、またもや
レディース達「あいや~〇〇さんとこの子だっちゃや~!」 ← えっ?皆さん知ってるの ?(心の声)
?(心の声)
「今日はお姑さんもいるから緊張するの~ww」 ← なにプレッシャーかけてんな (心の叫び)
(心の叫び)
学芸員さんなんだかおののいて苦笑い←がんばれ! (心から応援)
(心から応援)
地元だと「人類みな知ってる」みたいな勢いですごいな・・・嫁できた私には分からない世界・・・
「みなさん知っている方々ばかりなので、緊張します~ がんばりますのでよろしくお願いします~
がんばりますのでよろしくお願いします~ 」とスマイルで説明開始。
」とスマイルで説明開始。
「がんばれ学芸員さん 」と心の中で嫁エール
」と心の中で嫁エール
大笈酒(おおおいさけ)の展示コーナーは撮影禁止なので、写真は学芸員さんが頑張って説明中のこれ一枚

すごく簡単に、自分なりに解釈すると、
羽黒山では毎年、大みそかから元旦にかけて「松例祭(しょうれいさい)」が行われています。「松聖(まつひじり)」と呼ばれる2人の山伏が天下泰平・国土安穏・五穀豊穣・万民快楽を祈願し100日間修行しますが、この100日間の修行と松例祭を羽黒山伏の「冬の峰」と呼び、この峰中に神事として行われていたのが「大笈酒」なんだそうです。
冬の峰に携わる人々が出羽三山の神仏と一体となる重要な「食」の神事ですが、料理に使われた材料は123種、品数は25種類といわれ、超豪華な精進料理だったのですが、あまりに材料準備が大変で、お金がかかるし負担が多すぎということで廃止され、今となっては幻になってしまったけれど、近年古文書や古老からの聞き取りによって過去2度復元されて、今回いでは文化記念館で紹されているのだという。
説明もなしに、ただ展示品を眺めただけでは全く知りえなかった歴史が、学芸員さんの非常にわかりやすい説明で、一同感心
精進料理は初めは山伏の自給自足の料理から派生したとのことですが、ここまで豪華になり、地域に根差すとは、羽黒山 精進料理の奥深さ・・・改めてすごいです!
形はそのままでも、味は現代に合わせて薄味に変化しているそうです。
そこで、見せていただいたのがこれ!

「しそ巻」というもので、ガラスケースの中にあるレプリカの本物版!!
なんと神林坊さんにお手伝いに来ているおばあちゃんからの差し入れなんだそうです。歴史のなかの精進料理が目の前にあるという事で、みんな大興奮!!(特に私 )
)
厚揚げで、中にシソをいれてのり巻きのように巻いて、い草でしばり、砂糖・醤油・酒の味付けで1時間くらい煮て、最後に油で揚げるとのこと。
切ると、ロールケーキの様に見えるのですよ!
すごい~ 普通に作ってるんだ・・・
普通に作ってるんだ・・・
「食べてみたい!」と思ったものの、26等分は一人一体何ミリ?と思ったので、さすがに言葉に出すのはあきらめましたw
他にも歴史学者さんの大笈酒の説明のビデオや料理など様々な写真や資料があり、精進料理の隠語(隠れた意味を持つ名)なども写真付きで展示してあり、それに対し一つ一つ丁寧に説明していただき、ただ来ただけでは味わえなかった満足感でイッパーイ
わたし侮ってました・・・すみません。大笈酒すごいです
11月26日まで いでは文化記念館で展示会しておりますので、皆さん一度見に行ってみてください!!
数名でまとまっていらっやるなら、事前に連絡いただけるなら学芸員さんが案内してくれるそうです!!
絶対説明してもらいながら見ることをおすすめします!また声をかけてくだされば、事務所にいるときなら案内いたしますよ~とのこと。
ただ見ただけではわからないことがいっぱい分かりますよ
当初30分位の見学予定だったのが、30分ほどオーバーしてしまいましたが、あまりの説明の素晴らしさに皆感動し、だれも文句も言わず「いや~来ていがったの~ 」の感想を口々に斎館に向かうのでした
」の感想を口々に斎館に向かうのでした
斎館編につづく

精進料理をお昼にいただく予定ですが、ただ食べるのでは研修の意味がないので、精進料理の歴史を学ぼうと、
「 日本一の品数といわれる羽黒山に伝わるもっとも豪華な精進料理
 幻の精進料理「大笈酒(おおおいさけ)」 」
幻の精進料理「大笈酒(おおおいさけ)」 」のお勉強をさせていただきました。「お」がやたらと多いので、「お~いさけ」と呼びがちですが(私だけ
 ?)、「おお おい さけ」なんですよ!
?)、「おお おい さけ」なんですよ!
勉強するにあたり、「学芸員さんから案内してもらいましょう」と成瀬さんから提案をいただいた際、「いではに学芸員さんっているんですか
 ?」と思わず驚いてしまいました。すみません
?」と思わず驚いてしまいました。すみません いではの存在意義がわかってなーい
いではの存在意義がわかってなーい
どやどやと受付を済ますと、なんだか華奢でかわいらしい方が登場。
「もしや彼女が学芸員さん?!
 」とワクワクしていたら、またもや
」とワクワクしていたら、またもやレディース達「あいや~〇〇さんとこの子だっちゃや~!」 ← えっ?皆さん知ってるの
 ?(心の声)
?(心の声) 「今日はお姑さんもいるから緊張するの~ww」 ← なにプレッシャーかけてんな
 (心の叫び)
(心の叫び)学芸員さんなんだかおののいて苦笑い←がんばれ!
 (心から応援)
(心から応援)地元だと「人類みな知ってる」みたいな勢いですごいな・・・嫁できた私には分からない世界・・・
「みなさん知っている方々ばかりなので、緊張します~
 がんばりますのでよろしくお願いします~
がんばりますのでよろしくお願いします~ 」とスマイルで説明開始。
」とスマイルで説明開始。「がんばれ学芸員さん
 」と心の中で嫁エール
」と心の中で嫁エール
大笈酒(おおおいさけ)の展示コーナーは撮影禁止なので、写真は学芸員さんが頑張って説明中のこれ一枚

すごく簡単に、自分なりに解釈すると、
羽黒山では毎年、大みそかから元旦にかけて「松例祭(しょうれいさい)」が行われています。「松聖(まつひじり)」と呼ばれる2人の山伏が天下泰平・国土安穏・五穀豊穣・万民快楽を祈願し100日間修行しますが、この100日間の修行と松例祭を羽黒山伏の「冬の峰」と呼び、この峰中に神事として行われていたのが「大笈酒」なんだそうです。
冬の峰に携わる人々が出羽三山の神仏と一体となる重要な「食」の神事ですが、料理に使われた材料は123種、品数は25種類といわれ、超豪華な精進料理だったのですが、あまりに材料準備が大変で、お金がかかるし負担が多すぎということで廃止され、今となっては幻になってしまったけれど、近年古文書や古老からの聞き取りによって過去2度復元されて、今回いでは文化記念館で紹されているのだという。
説明もなしに、ただ展示品を眺めただけでは全く知りえなかった歴史が、学芸員さんの非常にわかりやすい説明で、一同感心

精進料理は初めは山伏の自給自足の料理から派生したとのことですが、ここまで豪華になり、地域に根差すとは、羽黒山 精進料理の奥深さ・・・改めてすごいです!
形はそのままでも、味は現代に合わせて薄味に変化しているそうです。
そこで、見せていただいたのがこれ!

「しそ巻」というもので、ガラスケースの中にあるレプリカの本物版!!
なんと神林坊さんにお手伝いに来ているおばあちゃんからの差し入れなんだそうです。歴史のなかの精進料理が目の前にあるという事で、みんな大興奮!!(特に私
 )
)厚揚げで、中にシソをいれてのり巻きのように巻いて、い草でしばり、砂糖・醤油・酒の味付けで1時間くらい煮て、最後に油で揚げるとのこと。
切ると、ロールケーキの様に見えるのですよ!
すごい~
 普通に作ってるんだ・・・
普通に作ってるんだ・・・「食べてみたい!」と思ったものの、26等分は一人一体何ミリ?と思ったので、さすがに言葉に出すのはあきらめましたw
他にも歴史学者さんの大笈酒の説明のビデオや料理など様々な写真や資料があり、精進料理の隠語(隠れた意味を持つ名)なども写真付きで展示してあり、それに対し一つ一つ丁寧に説明していただき、ただ来ただけでは味わえなかった満足感でイッパーイ

わたし侮ってました・・・すみません。大笈酒すごいです

11月26日まで いでは文化記念館で展示会しておりますので、皆さん一度見に行ってみてください!!
数名でまとまっていらっやるなら、事前に連絡いただけるなら学芸員さんが案内してくれるそうです!!
絶対説明してもらいながら見ることをおすすめします!また声をかけてくだされば、事務所にいるときなら案内いたしますよ~とのこと。
ただ見ただけではわからないことがいっぱい分かりますよ

当初30分位の見学予定だったのが、30分ほどオーバーしてしまいましたが、あまりの説明の素晴らしさに皆感動し、だれも文句も言わず「いや~来ていがったの~
 」の感想を口々に斎館に向かうのでした
」の感想を口々に斎館に向かうのでした
斎館編につづく