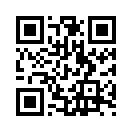2012年10月15日
鶴岡食文化女性リポーター 山ぶどう編レポ その1
最近お仕事をアップしていませんが、多くの方に知ってほしいので、このたびの鶴岡食文化女性リポーター活動のレポートを上げさせていただきます~
我が家には、栗・アケビ・すもも・くるみ・ぶどう等など個人の家にしては実のなる木を多く栽培しており(一応左官屋ですよ~ )、この度の「鶴岡女性リポーター第4弾山編」では、野生のブドウを栽培している方からお話が聞けるので、すごく楽しみにしておりました。
)、この度の「鶴岡女性リポーター第4弾山編」では、野生のブドウを栽培している方からお話が聞けるので、すごく楽しみにしておりました。
天気が悪かったので、完全防備の為に、我が家で交通誘導で使用するカッパ上下着込んで臨みました
今回の講師は、なんば農園(山ぶどう農家)の難波裕一さんです。お爺ちゃんの代から山ブドウを栽培。日本で初めて鶴岡で山ぶどうの栽培を確立したそうです!

昔、朝日にはこれといった作物がなく、山葡萄を特産にしてはどうだろう?と試行錯誤の連続で栽培を始めたそうです。
挿し木にしても生えたけど3~5年たっても実がならず、山形大学と共同研究し、数年かかってブドウの木には雄雌があるのを発見!それでも実がならず、さらに受粉が必要だった!とわかって、受粉したところようやく結実に成功し、今日に至ったそうです 。
。
このお話を聞いたとき、イチョウやあけびも結実するには雌雄の木が必要なので、山ぶどうもまた太古からある木の一つなのだな~と思いました。子孫を残すのに雌雄どちらが欠けてもいけないなんて、木だけどなんだか素敵ですね
そして野生種からの栽培なので、個体によって味が異なるそうです。今は雌木10本に1本の雄木の割合で植えているけど、雄の木の花を農協に持っていき、花粉を取り出してもらい、受粉は機械で行うとのこと。
すぐりもぎはせず、ツルの剪定は夏に行う。10月は鳥や猿の被害があり、猿は団体でやってくるので追い払うのが大変なのだそうです。
今見ている山ブドウが長年の努力のもとで、こうして私たちの手に届いてるとわかり感動 。
。
現在栽培者は100名ほどで、ぶどう部会として活動しているとのこと。
皆がみな栽培方法が違うので、それぞれが先生なんだそうです(それもまたすごい !)
!)
他県でも山ぶどうを栽培しているそうですが、なり方・収穫量からしても朝日が№1と自負。現在、朝日1号・月山1~5号まであり、1~2号は9月いっぱい、3~5号は11月まで収穫できるそうです。「見分け方は?」と質問したら、「一番早くなったのが1号ww」とのこと。アバウト~
朝日地域でも山ぶどうの原液は、お客さんがきても飲ませない。自分の薬としておちょこで少しずつ飲んだそうです。
昔から鶴岡の地元でも滋養の薬として広く飲まれており、私も妊婦の時は「貧血予防と血行よくなるから飲みなさい~」と義母に進められて飲んでました。しかし、その時にのんでいた山ぶどうの原液は、顔が最強しかめっ面 になるほど酸っぱいものだったので、今回の山ぶどう原液も同じなのかとドキドキしながらのんだら「あれっ?山ぶどう?」と思うほど美味しい。
になるほど酸っぱいものだったので、今回の山ぶどう原液も同じなのかとドキドキしながらのんだら「あれっ?山ぶどう?」と思うほど美味しい。
隣にいたツアーの方も「なんだか酸っぱくて美味しいわ~運動してないのに、体がぽかぽかするわ~ 」と不思議がってます。早速血行が良くなったのですね!効果早いな~
」と不思議がってます。早速血行が良くなったのですね!効果早いな~
「この山ぶどうは酸っぱくない 」というと、「それは品種の違いですよ
」というと、「それは品種の違いですよ 」と難波さん。
」と難波さん。
ううううっ あの時こういう山ブドウ原液飲みたかったです・・・
あの時こういう山ブドウ原液飲みたかったです・・・
お話の合間に、山からとってきました~というキノコ汁がふるまわれ、
 見たこともないキノコがたくさん入ってましたが、すっごい美味し~。
見たこともないキノコがたくさん入ってましたが、すっごい美味し~。
ちなみに赤いきのこは「ますたけ」だそうです。
食べ終わると、早速準備して頂いた山ぶどうでジュース作り。山ブドウワインは糖度18度以上のものを使うのですが、今回準備していただいたのは、17~18度のブドウ。
手で房から粒を取りますが、野生種なゆえかしっかりついているので、ぶちっと引っ張って取らないとなかなか取れない。ホントに山に生えてるブドウは、もっと粒がバラバラで小さい感じなのですが、作付した山ぶどうは粒も大きく、沢山ついています。

房をなんとかはずし、つぶす段階で「踏んでもいいですよ」と言われたので、ふみふみ。
なんとも言えない ぷちぶち感覚wおもしろーい

ウキウキ踏んでいたら、「踏みすぎてビニール切らさないように気を付けてくださいね~ 」と言われ、途中から慎重にフミフミ。
」と言われ、途中から慎重にフミフミ。
つぶした山ぶどうは1週間おいてからザルでこして皮と液体に分け、液体はペットボトルに入れて保管。皮は再度水と砂糖を入れて煮だすと、2番ジュースができるそうです。漬物の色付けにも使ったり、さまざま最後まで使い切るそうです。種が4つも入ってるので、干しブドウとか加工食品には向かないとのこと。
そして山ぶどう原液で作ったジャムとその」山ぶどう原液を飲ませて頂きました!


ジャムすっごいおいしい~そのまま全部食べられる~と一同笑顔。ブドウ色なのに、普通のブドウとは違うしっかりした味!
原液はボトルごと味が少しずつ違う。3杯も飲むと冷え性な私も体がぽかぽかしてきて、さすが昔からお薬と重宝されているのがわかります。「ちょっと山に登ってきます!」と思わず言ってしまいそうな勢いです
原液だと長期保存可能で、1年くらいになるとワイン状態になるそうです 。
。
鶴岡に住んでいながら、知らないことが沢山あるな~とまたこのリポーター活動で学びました。鶴岡の食文化は深いデス
山ぶどうがこんなにおいしく気軽に頂けるのは、やはり長年苦労を重ねて栽培してきてくれた難波さんたちのおかげだなあと思いつつ、今度はその山ぶどうの畑に連れていってくださるそうです。
どんな風な畑?なのか楽しみ~♪
その2へ続く

我が家には、栗・アケビ・すもも・くるみ・ぶどう等など個人の家にしては実のなる木を多く栽培しており(一応左官屋ですよ~
 )、この度の「鶴岡女性リポーター第4弾山編」では、野生のブドウを栽培している方からお話が聞けるので、すごく楽しみにしておりました。
)、この度の「鶴岡女性リポーター第4弾山編」では、野生のブドウを栽培している方からお話が聞けるので、すごく楽しみにしておりました。天気が悪かったので、完全防備の為に、我が家で交通誘導で使用するカッパ上下着込んで臨みました

今回の講師は、なんば農園(山ぶどう農家)の難波裕一さんです。お爺ちゃんの代から山ブドウを栽培。日本で初めて鶴岡で山ぶどうの栽培を確立したそうです!

昔、朝日にはこれといった作物がなく、山葡萄を特産にしてはどうだろう?と試行錯誤の連続で栽培を始めたそうです。
挿し木にしても生えたけど3~5年たっても実がならず、山形大学と共同研究し、数年かかってブドウの木には雄雌があるのを発見!それでも実がならず、さらに受粉が必要だった!とわかって、受粉したところようやく結実に成功し、今日に至ったそうです
 。
。このお話を聞いたとき、イチョウやあけびも結実するには雌雄の木が必要なので、山ぶどうもまた太古からある木の一つなのだな~と思いました。子孫を残すのに雌雄どちらが欠けてもいけないなんて、木だけどなんだか素敵ですね

そして野生種からの栽培なので、個体によって味が異なるそうです。今は雌木10本に1本の雄木の割合で植えているけど、雄の木の花を農協に持っていき、花粉を取り出してもらい、受粉は機械で行うとのこと。
すぐりもぎはせず、ツルの剪定は夏に行う。10月は鳥や猿の被害があり、猿は団体でやってくるので追い払うのが大変なのだそうです。
今見ている山ブドウが長年の努力のもとで、こうして私たちの手に届いてるとわかり感動
 。
。現在栽培者は100名ほどで、ぶどう部会として活動しているとのこと。
皆がみな栽培方法が違うので、それぞれが先生なんだそうです(それもまたすごい
 !)
!)他県でも山ぶどうを栽培しているそうですが、なり方・収穫量からしても朝日が№1と自負。現在、朝日1号・月山1~5号まであり、1~2号は9月いっぱい、3~5号は11月まで収穫できるそうです。「見分け方は?」と質問したら、「一番早くなったのが1号ww」とのこと。アバウト~

朝日地域でも山ぶどうの原液は、お客さんがきても飲ませない。自分の薬としておちょこで少しずつ飲んだそうです。
昔から鶴岡の地元でも滋養の薬として広く飲まれており、私も妊婦の時は「貧血予防と血行よくなるから飲みなさい~」と義母に進められて飲んでました。しかし、その時にのんでいた山ぶどうの原液は、顔が最強しかめっ面
 になるほど酸っぱいものだったので、今回の山ぶどう原液も同じなのかとドキドキしながらのんだら「あれっ?山ぶどう?」と思うほど美味しい。
になるほど酸っぱいものだったので、今回の山ぶどう原液も同じなのかとドキドキしながらのんだら「あれっ?山ぶどう?」と思うほど美味しい。隣にいたツアーの方も「なんだか酸っぱくて美味しいわ~運動してないのに、体がぽかぽかするわ~
 」と不思議がってます。早速血行が良くなったのですね!効果早いな~
」と不思議がってます。早速血行が良くなったのですね!効果早いな~
「この山ぶどうは酸っぱくない
 」というと、「それは品種の違いですよ
」というと、「それは品種の違いですよ 」と難波さん。
」と難波さん。ううううっ
 あの時こういう山ブドウ原液飲みたかったです・・・
あの時こういう山ブドウ原液飲みたかったです・・・お話の合間に、山からとってきました~というキノコ汁がふるまわれ、

 見たこともないキノコがたくさん入ってましたが、すっごい美味し~。
見たこともないキノコがたくさん入ってましたが、すっごい美味し~。ちなみに赤いきのこは「ますたけ」だそうです。
食べ終わると、早速準備して頂いた山ぶどうでジュース作り。山ブドウワインは糖度18度以上のものを使うのですが、今回準備していただいたのは、17~18度のブドウ。
手で房から粒を取りますが、野生種なゆえかしっかりついているので、ぶちっと引っ張って取らないとなかなか取れない。ホントに山に生えてるブドウは、もっと粒がバラバラで小さい感じなのですが、作付した山ぶどうは粒も大きく、沢山ついています。

房をなんとかはずし、つぶす段階で「踏んでもいいですよ」と言われたので、ふみふみ。
なんとも言えない ぷちぶち感覚wおもしろーい

ウキウキ踏んでいたら、「踏みすぎてビニール切らさないように気を付けてくださいね~
 」と言われ、途中から慎重にフミフミ。
」と言われ、途中から慎重にフミフミ。つぶした山ぶどうは1週間おいてからザルでこして皮と液体に分け、液体はペットボトルに入れて保管。皮は再度水と砂糖を入れて煮だすと、2番ジュースができるそうです。漬物の色付けにも使ったり、さまざま最後まで使い切るそうです。種が4つも入ってるので、干しブドウとか加工食品には向かないとのこと。
そして山ぶどう原液で作ったジャムとその」山ぶどう原液を飲ませて頂きました!


ジャムすっごいおいしい~そのまま全部食べられる~と一同笑顔。ブドウ色なのに、普通のブドウとは違うしっかりした味!
原液はボトルごと味が少しずつ違う。3杯も飲むと冷え性な私も体がぽかぽかしてきて、さすが昔からお薬と重宝されているのがわかります。「ちょっと山に登ってきます!」と思わず言ってしまいそうな勢いです

原液だと長期保存可能で、1年くらいになるとワイン状態になるそうです
 。
。鶴岡に住んでいながら、知らないことが沢山あるな~とまたこのリポーター活動で学びました。鶴岡の食文化は深いデス

山ぶどうがこんなにおいしく気軽に頂けるのは、やはり長年苦労を重ねて栽培してきてくれた難波さんたちのおかげだなあと思いつつ、今度はその山ぶどうの畑に連れていってくださるそうです。
どんな風な畑?なのか楽しみ~♪
その2へ続く
Posted by のりえもん at 16:05│Comments(0)
│行事その他